「この業務、やる意味ありますか?」
もし、あなたが心の中でそう思ったとしても――
口に出すのはちょっと、いや、だいぶ怖いですよね。
だって、そんなことを言おうものなら、次の日から職員室の空気が変わる。
あからさまにじゃなくても、なにか“ひんやり”した感じが漂う。
これは僕自身も経験したことがあるし、
同じような若手の先生が、発言したことで孤立していくのも何度も見てきました。
正論では、勝てないことがある
初任者に限らず、若手の先生がよく抱えるジレンマ。
それは、「これっておかしくない?」と思っても、言えないこと。
言ってしまったらどうなるか。
- 「わかってないね」と小馬鹿にされる
- 「若いくせに口だけ達者」と嫌味を言われる
- 「空気読めない子」と遠巻きにされる
それだけならまだしも――
周囲の先生たちが、少しずつ距離を取り始める。
雑談に入れなくなる。
「言わなきゃよかった」と後悔する。
…そうやって、自分の“居場所”がなくなっていく。
だから、正論を口にできない。
理不尽を見過ごすしかない。
それが今の多くの現場のリアルなんです。
「正しい」よりも「戦える」戦略を
じゃあ、どうすればいいのか?
僕の出した答えはこれでした。
正義感だけで突っ込まず、“一緒に言ってくれる味方”を見つけること。
そう。
「正論でぶつかる」じゃなくて、
「波に乗せて発言してもらう」ことが、大事なんです。
“味方づくり”という、生き延びる術
本音を言うと、若手だけで現場の構造を変えるのは無理です。
でも、「自分一人じゃない」と思えるだけで、ほんの少し楽になります。
だから、最初にやるべきことは――
“意見を代弁してくれる、信頼できる中堅以上の先生”を見つけること。
たとえば、
- 気さくで話しかけやすい教務主任
- 自分のことを気にかけてくれる学年の先生
- 職員室でひと声かけてくれる教頭先生 など
はじめは雑談からでも大丈夫。
少しずつ関係性を築いていって、
「ちょっと、こういうことで悩んでて…」と打ち明けてみる。
その人が、代わりに会議の場で発言してくれるかもしれない。
あなたが言うよりも、ずっと波風を立てずに、影響力を発揮してくれるかもしれない。
それだけで、状況は少しずつ変わっていくんです。
“見えない地雷”が多すぎる
もうひとつ伝えたいのは、
「学校には、見えない地雷が多すぎる」ということ。
- 実は昔トラブルになった行事のやり方
- PTAの間で評判が悪かった保護者対応
- 管理職の好みによって変わる報告の順番
- 「今年からなくしたい」と思ってるけど誰も口に出せない仕事
そういった“前例・しがらみ・不文律”があちこちに転がっていて、
それを知らずに触れると、「空気読めない」と思われる。
若手が失敗するのは、「やる気がないから」ではありません。
“ルールが見えていない”のに、“一人前のように扱われてしまう”からなんです。
戦略は、自分を守るためにある
だからこそ、必要なのは「戦略」。
- 自分の意見を、誰に、どう伝えるか
- 自分が動く前に、誰にひと声かけておくか
- 本音を話せる“逃げ場”を、どこに持っておくか
そういう細やかな戦術を積み重ねることが、
この“理不尽すぎる現場”を、なんとか生き抜く術になる。
あなたの中に、「灯」を残すために
僕は思うんです。
先生って、誰かに褒められなくても、
自分の中に「灯」があるから頑張れる人たちだと思います。
でもね、その灯が風にあおられ続けたら、いつかは消えてしまう。
だからこそ、「消えないように守る工夫」を身につけてほしい。
それは逃げじゃなくて、自分を大切にするための戦い方です。
◆ 次回、「灯」を守るための方法へ
次回の第3話では――
そんな「灯」を守るために、
- 何が必要なのか
- “メンターがいない”学校でどう生き延びるのか
- 学校外の“味方”をどうつくるか
について、僕の経験も交えながらお話しします。
タイトルは、
「誰も教えてくれないなら、自分で“道”をつくるしかない」です。
一人でも多くの先生が、自分の中の光を守れますように。
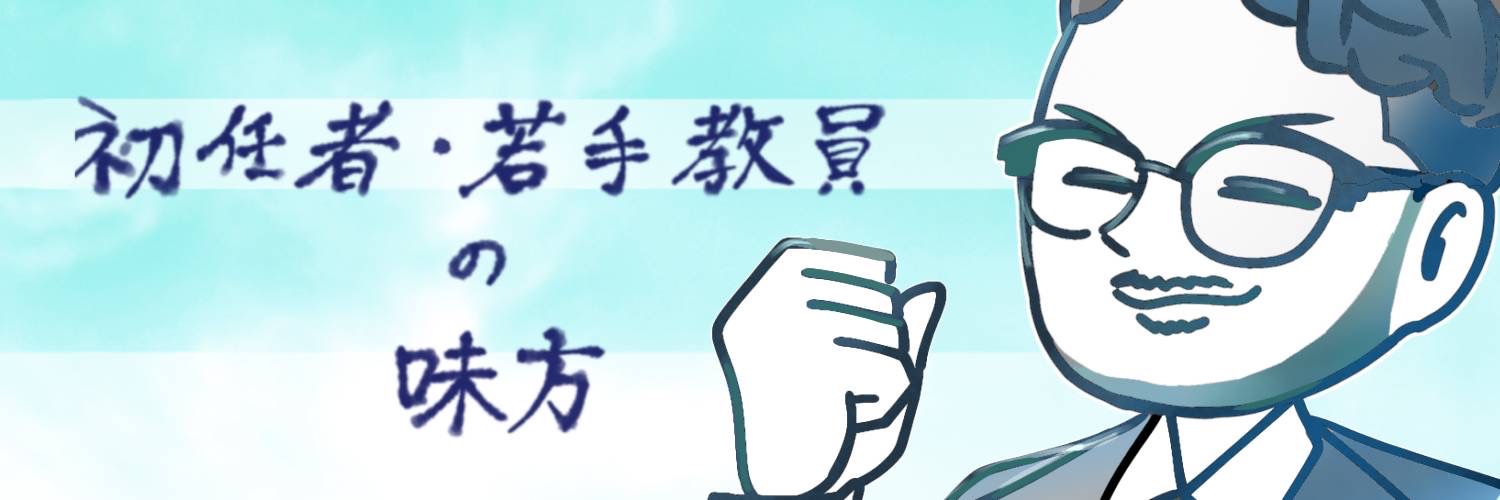
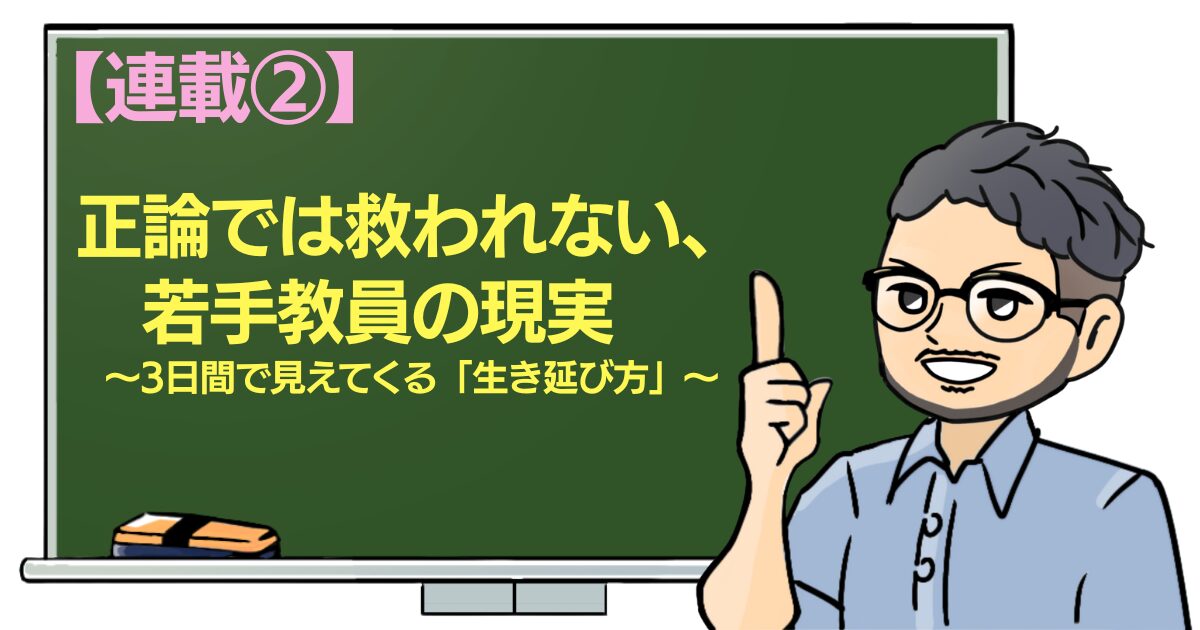


コメント