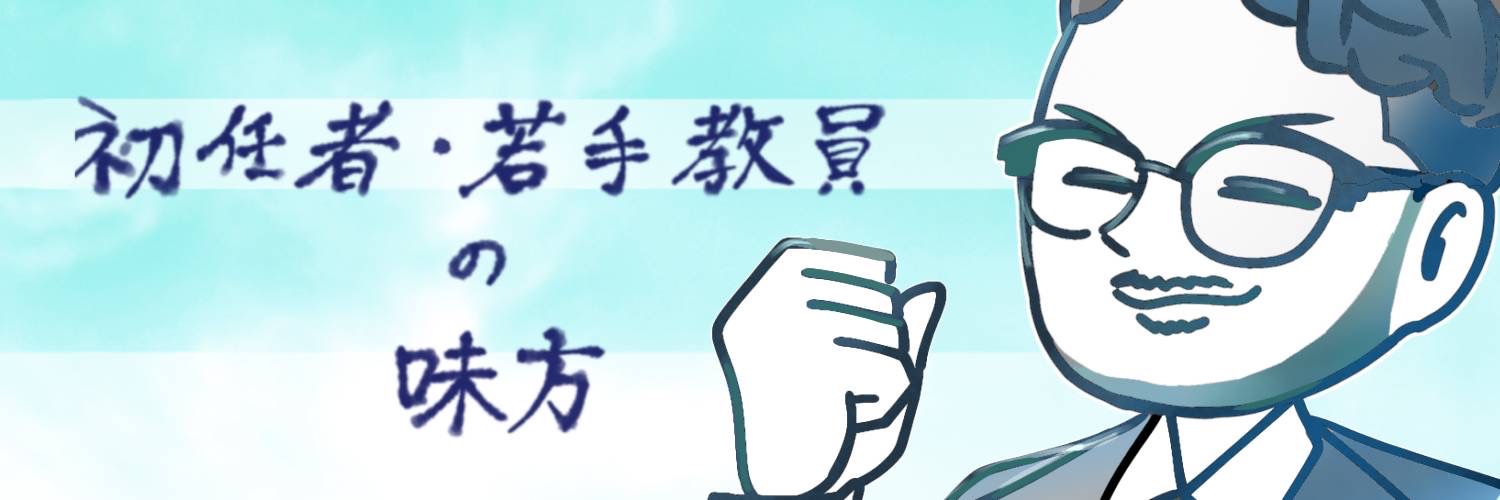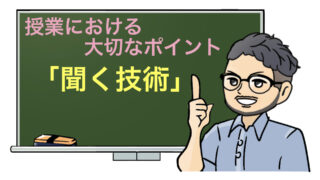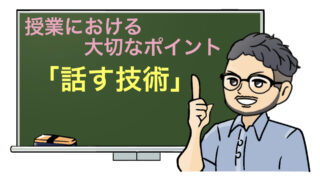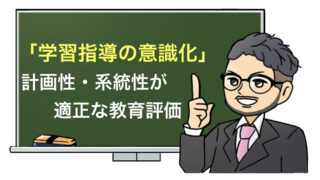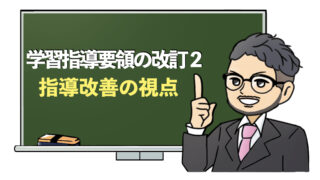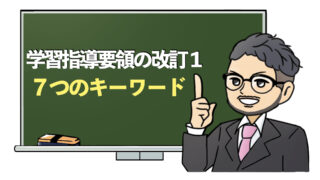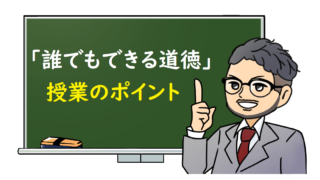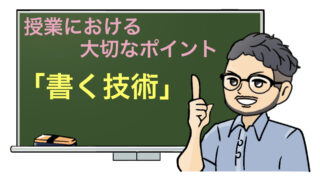 授業づくり
授業づくり 授業における大切なポイント「書く技術」
みなさん板書はしていますか?「字が下手だから」とか「PC使って授業しているから」などと言って板書を疎かにしていませんか?たしかに学校におけるICT化が加速し、タブレットやプロジェクタを使って、用意してきたスライドで授業をする機会も増えてきました。ですが、ノートを使った授業がなくなったわけではありません。板書は児童・生徒にとってノートのお手本です。教員が明確な意図を持って板書をする必要があります。今日は、板書をする際に意識したいポイントを紹介します。