「特殊教育」から「特別支援教育」に変わって15年。
もう10年もしないうちに「インクルージョン」は当たり前のこととなるでしょう。
インクルージョン = 健常児と障害児、つまり障害の有無といった視点ではなく、生徒一人ひとりに会った教育を行うこと
今までよりさらに多くの支援を必要とする児童・生徒がクラスに増えた状況で「どう授業を行うか」「どのように学級づくりを進めるか」これからの先生には大きな課題といえます。
その際に必要となるのが「知識と配慮」です。
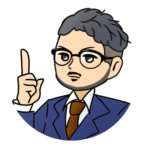
「言葉」1つで保護者との関係が変わってしまうこともあります。
「病名・障害名」変化に伴う「配慮」、ここから発達障害の理解を深めていきましょう。
精神疾患の病名変更
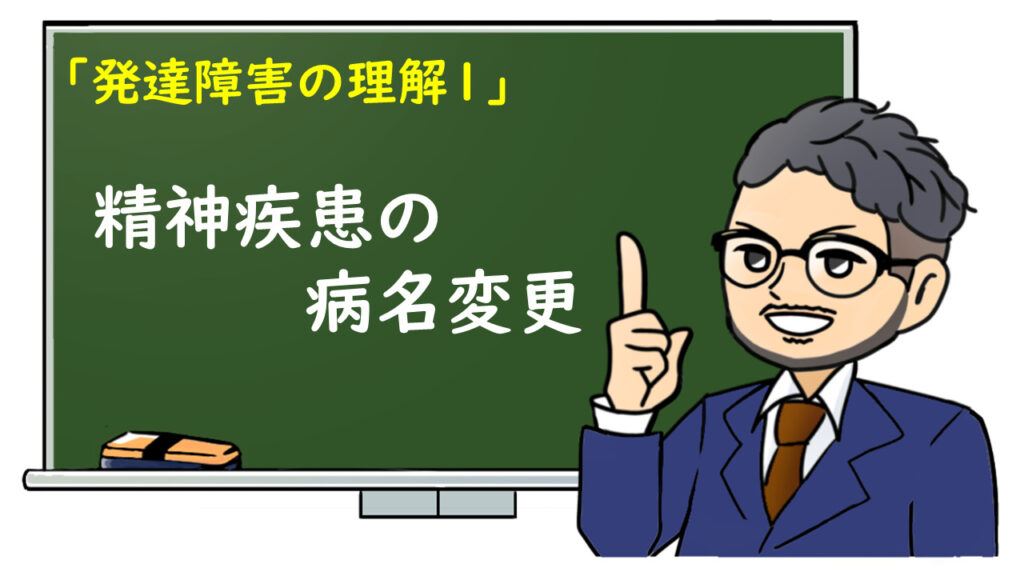
平成25年5月に米国精神医学会の精神疾患診断基準(DSM:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)が改定され、これに伴い日本精神神経学会が平成26年に精神疾患の病名を変更しました。
以下はその一部です。
「学習障害」 → 「限局性学習障害」(LD)
「アスペルガー障害」「高機能自閉症」「自閉症」 → 「自閉スペクトラム症」(ASD)
「注意欠陥・多動性障害」 → 「注意欠如・多動症」(AD/HD)
「パニック障害」 → 「パニック症」
「性同一性障害」 → 「性別違和」
「神経性無食欲症(拒食症)」 → 「神経性やせ症」(AN)
関連する「手帳」
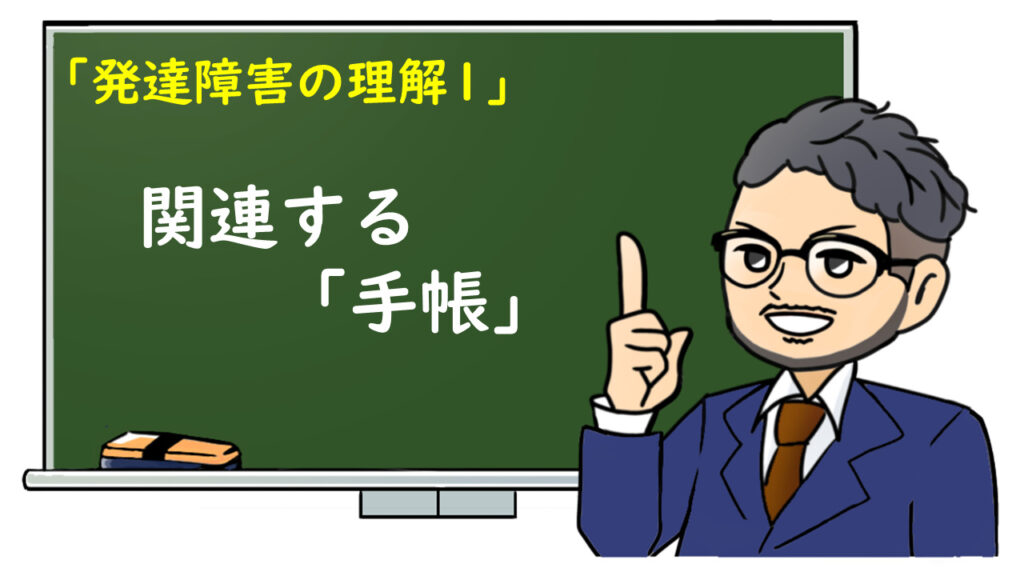
障害者手帳は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類を総称して呼びます。それぞれの関連についても押さえておきましょう。
| 身体障害者手帳 | 療育手帳 (愛の手帳) | 精神障害者保健福祉手帳 | |
| 対象となる障害 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 |
| 根拠となる法令等 | 身体障害者福祉法 | 各都道府県の条例等 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
| 手続 | 障害福祉事務所等 | 18歳未満 →児童相談所 18歳以上 →知的障害者更生相談所 | 精神保健センター 精神医療センター等 |
なお、所管官庁は厚生労働省。
発行者は各都道府県知事(政令指定都市の長)となります。
おわりに
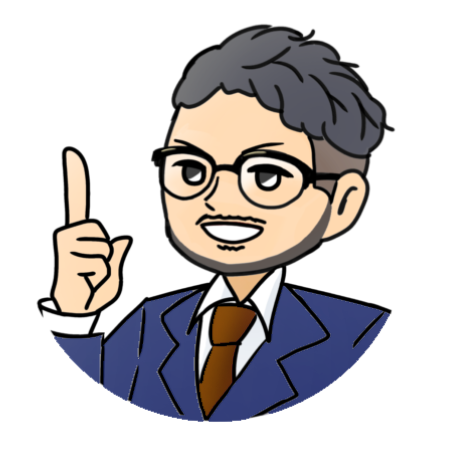
今回は、病名・障害名の変化に伴う配慮について紹介しました。
次回は、発達障害の具体的な特徴などに触れていきたいと思います。
正しい知識をもって、指導にあたれるようにしていきたいですね。
コロナ対応等で大変な時期ですが、一緒にがんばりましょう。
春はもうすぐそこです。応援しています。
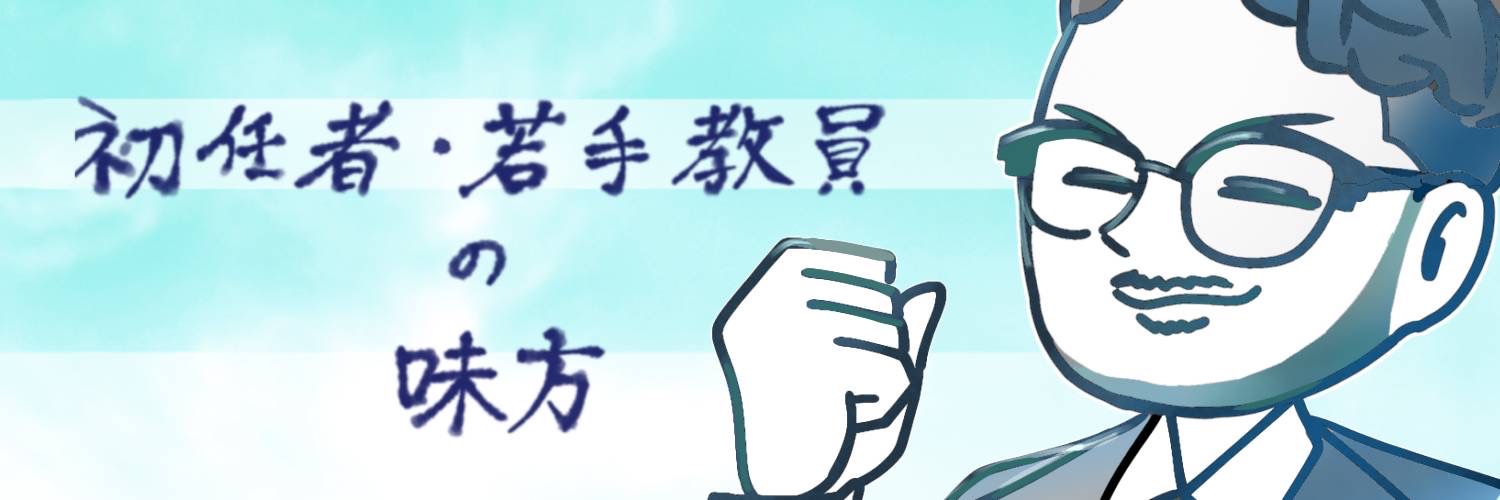
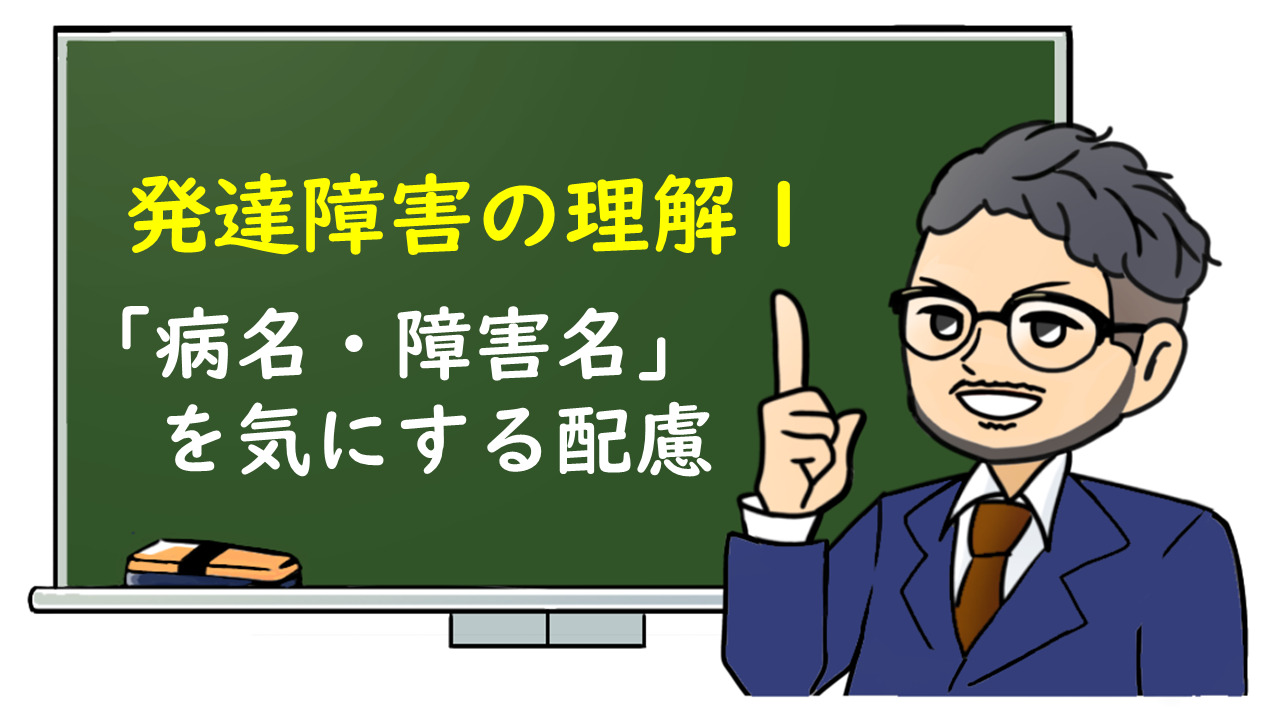
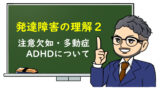
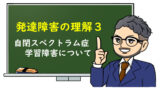


コメント