カリキュラム・マネジメントをしていく中で、なんとなく「改善」するということではいけません。
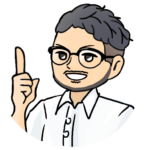
その時に必要になるのがエビデンスです。
ここ数年よく聞くようになったこの「エビデンス」とはなんでしょうか。
今回はエビデンスに基づいたカリキュラム・マネジメントのポイントを紹介していきます。
エビデンスって?
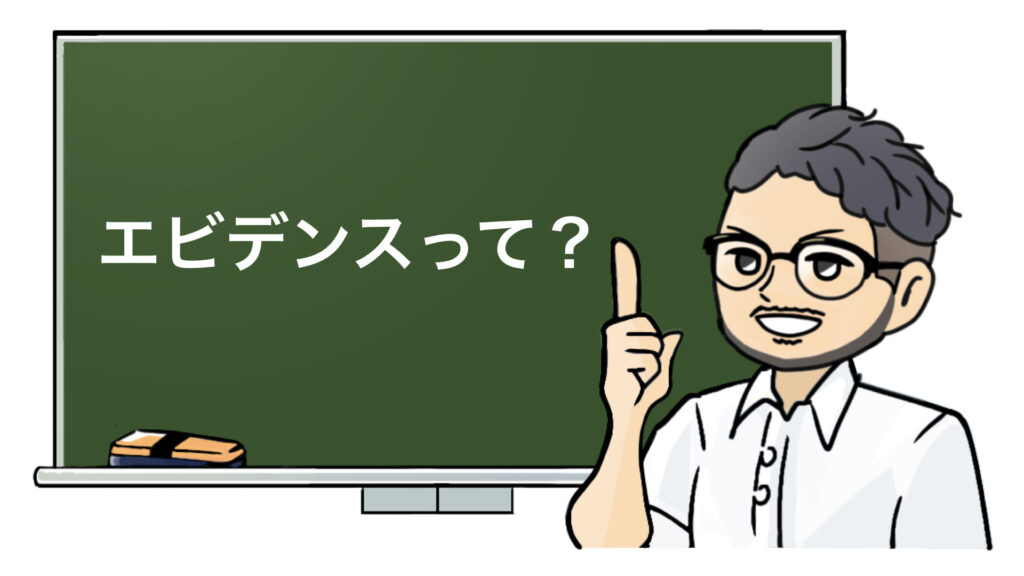
エビデンス(evidence)とは、「(科学的)根拠」や「証拠」を意味します。
エビデンスは評価資料や分析することから切り離せないものです。
きちんと理解しておきましょう。
評価資料「何が根拠になるのか」
分析「なぜ根拠になるのか」
エビデンスに基づいた「教育課程編成・改善・充実」と「授業改善」
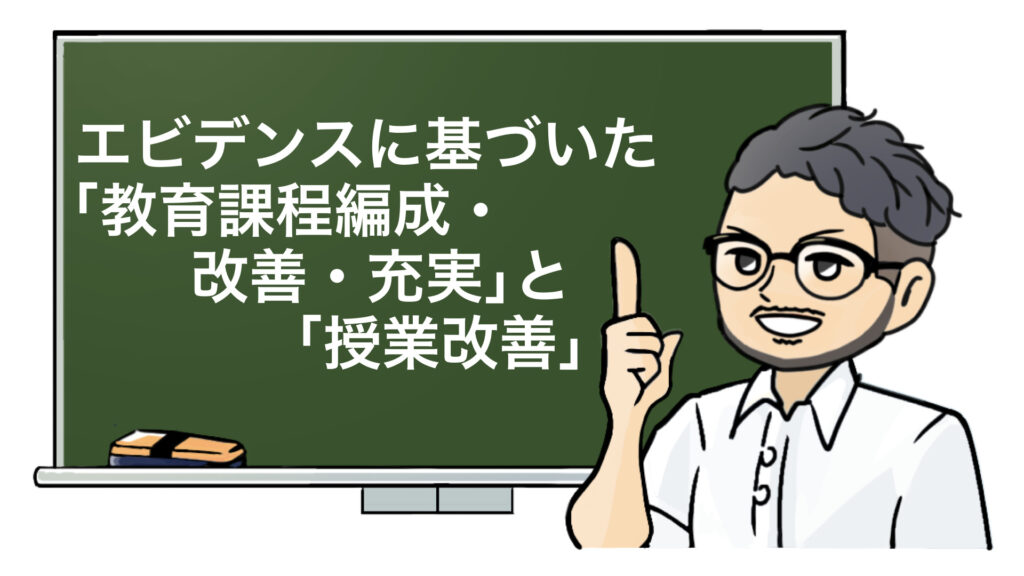
エビデンスに基づいた「教育課程編成・改善・充実」と「授業改善」は、客観的な分析に基づく「改善」です。
例を紹介します。
【例】授業改善
× 「生徒が分かっていないようだから、こうしよう」
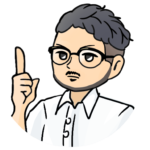
これでは、エビデンス(根拠)に基づいておらず、授業者の主観です。
◎ 「アンケートやテストの結果、ここが分かっていないから、こうしよう」
【例】教育課程
× 学校教職員の反省だけで、次年度の改善点を検討
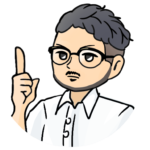
これでは、教職員目線でしか改善が行われません。
◎ 学校評価(保護者・児童・地域も含む)を分析して、次年度の改善点を検討
これからの授業づくり
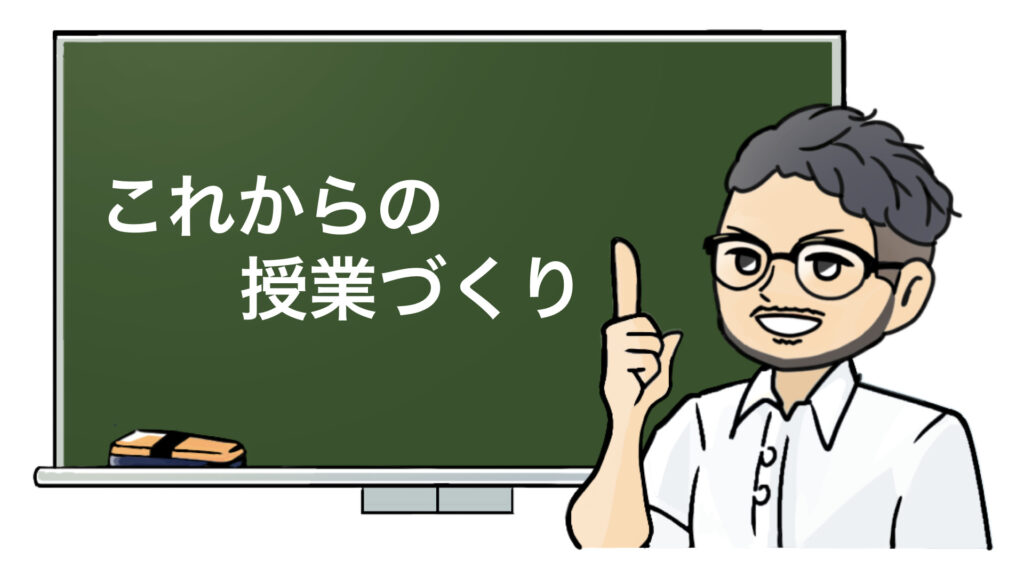
これからの授業には欠かせない4つのことがらです。
①カリキュラム・マネジメント
- 学校作りも授業づくりもPDCA
- 人的・物的資源の活用
- エビデンスに基づいた改善・改革
②主体的・対話的で深い学びの実現
- 問題解決学習
- 自己との対話・他者との対話
- 時間軸と空間軸、見方・考え方
③家庭・地域との連携
- 地域や保護者の力を有効活用
- コミュニティスクールの視点
- 学校評価の適切な分析
④評価の工夫
- 新しい3観点での評価計画
- 生徒が成長を実感(成就感)
- 学習過程で変容を把握可能な評価
主体的な学びの姿
キーワード:問題解決的学習
- 一人ひとりの目的意識が明確
- 問題解決の見直し
- 資料から意味・ポイント発見
- 目的に応じ必要事項を選択
- 自分の考えを組み立て
- 自分の意思決定、豊かに表現
- 達成感、充実感、学びがい
- 習得事項を生かした実践
- 新たな課題発見、追求の意欲 ほか
対話的な学びの姿
キーワード:自己との対話、他者との対話
- 資料を自分なりに考え、解釈
- 他人と討議・作業・実習・制作等協議的に学習
- 自らの考えを発信
- 他人の良さを発見・理解
- 多様な考えを調整、総括
- 人間関係の深化
- 協働する喜びの発見
- 協力し新しいものを想像 ほか
深い学び
キーワード:時間軸と空間軸、見方・考え方
- 日常生活に関する理解の深化
- 考え方・まとめ方の理解
- 考え方の変容
- より正しい判断をする力
- 日常生活への関心の拡大
- 応用力・発展力・思考力
- 見方・考え方が見えるものから見えないものに拡大(事実の認知から概念の認知へ) ほか
おわりに
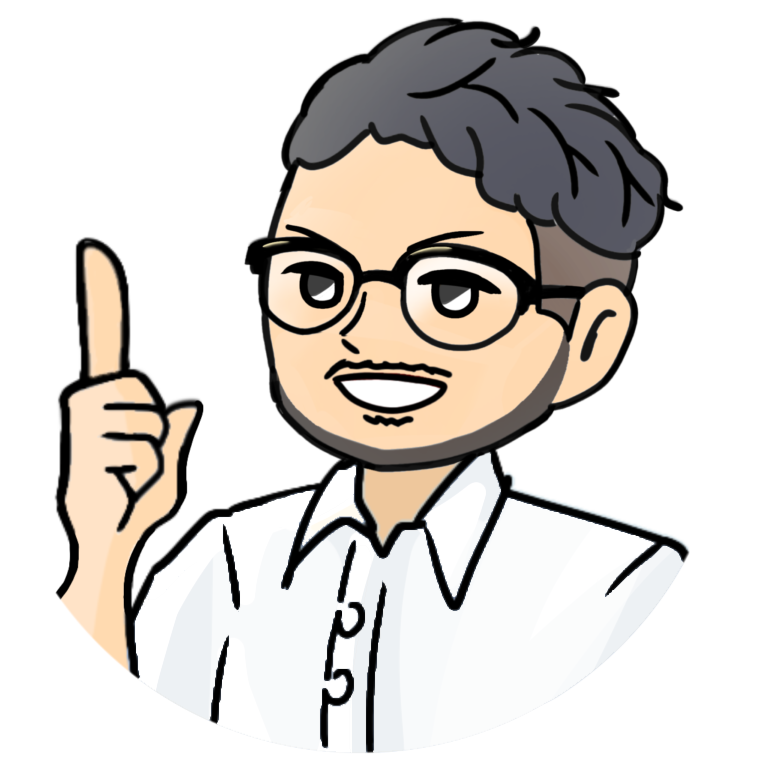
これからは「カリキュラム・マネジメント」、「主体的・対話的で深い学びの実現」、「家庭・地域との連携」、「評価の工夫」の四位一体で授業づくりをしていかなければなりません。
この夏は、そんな視点で教材研究に励んでみてはいかがでしょうか。
暑い中ですが、もう一踏ん張り頑張りましょう。
応援しています。
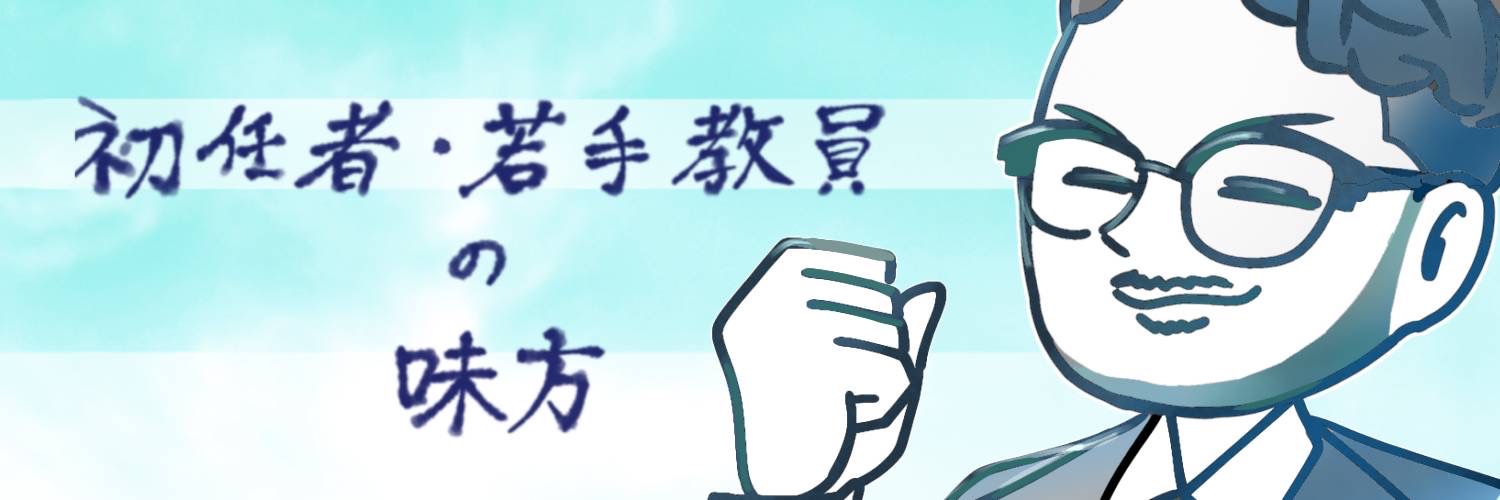



コメント