新年度まであとわずかとなりました。
今回は、春から教員になる先生たちに向けて、「私たち教員のするべきことは何か」というテーマを考えていきたいと思います。
今年初任だった先生は、今一度確認を。
そして、若手からベテランまで経験を重ねた先生も、自分の教育観や指導観を振り返る機会にしてもらえると嬉しいです。
教職員の仕事とは・・・
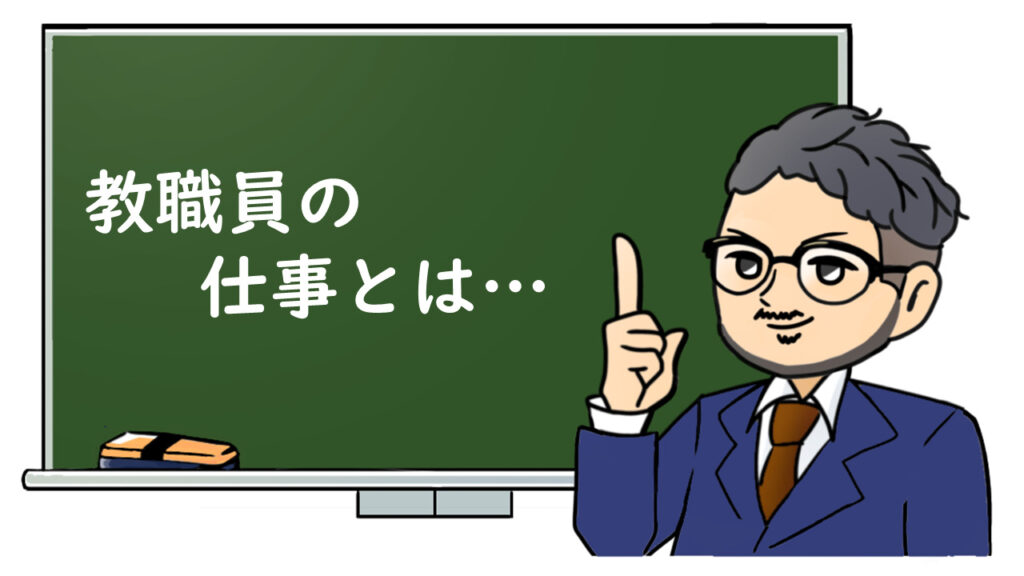
教職員の仕事は生徒の成長を支えることです。
各生徒の状況に合わせてできるようにすること(学習支援)
集団の取り組みを意識させてするべきことをさせること(行動支援)
自主・自立を意識させて考えさせる(自立支援)
私たちは、学習支援・行動支援・自立支援をすることになります。
そのためには・・・
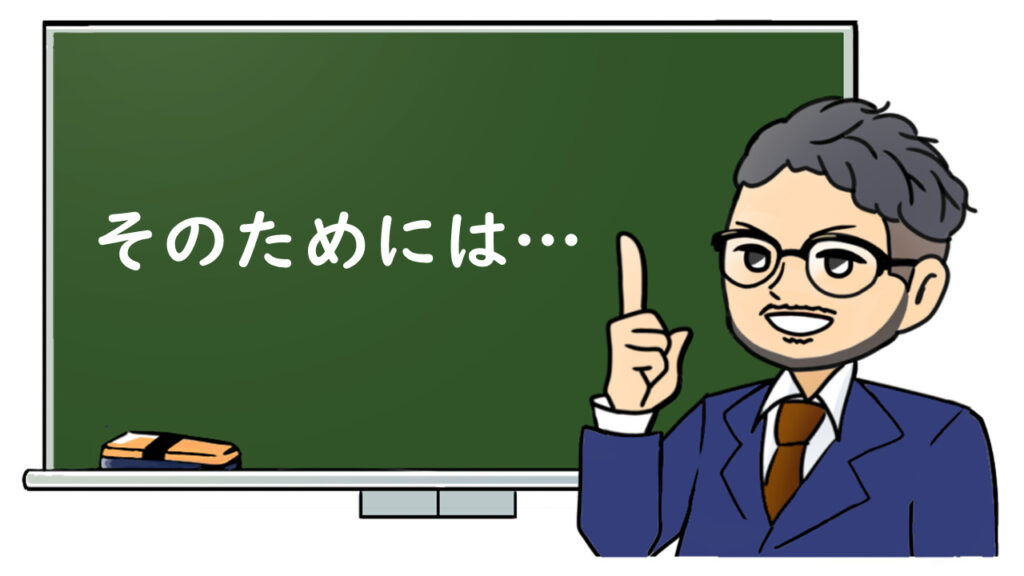
そのために必要なのは「指導」と「支援」です。
「指導」は「一貫性」と「厳しさ」です。
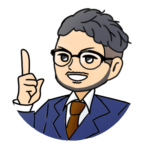
規範意識の育成の視点です。
「支援」は「粘り強さ」と「優しさ」です。
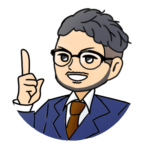
できるまで支援する意識が大切です。
注意しなければいけないのは、教員が「あの生徒はできない」と繰り返すことです。
これはある種「指導力がない」という宣言をしているようなものです。
教員の「プロ」としての発言・行動・指導を意識しましょう。
教職員としての意識は「teach」「coach」「facilitate」
大切にしたい3つの視点

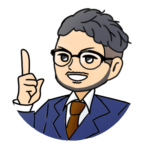
教職員の仕事の仕方で、大切にしたい3つの視点があります。
「感性」「スキル」「根拠」です。
「感性」 = 生徒の様子や変化、教師自身の客観的な自己変容に敏感であること
→ 情熱、愛情、客観性、効果性、感覚など
「スキル」 = 理論や経験に基づく、構造化された指導の技術
→ ソーシャルスキルトレーニング(SST)、指導技術(教科や全体指導)、特別支援など
「根拠」 = 指導や指示、検討、要望への回答の元となるもの
→ 法律、学習指導要領、通知、客観的学説、教育論、○○学など
「感性」がなければ、”血の通わない冷たい教員”と思われ、
「スキル」がなければ、”技術がなく実力のない教員”と思われ、
「根拠」がなければ、”考えない教員”と思われてしまいます。
初任者や若手教員は「感性」があれば大丈夫です。
「スキル」は現場で身につけていきましょう。
また、教採のために勉強しまくった「根拠」となる法律も、問題が起こってはじめてその大切さに気づきます。
なので、「根拠」となることがらは全部覚えていられなくても、いつでも調べられるよう手元に置いておきましょう。
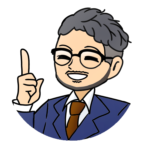
東アカのオープンセサミとか、捨てずにとっておくと便利ですよ。
手段と目的の明確化
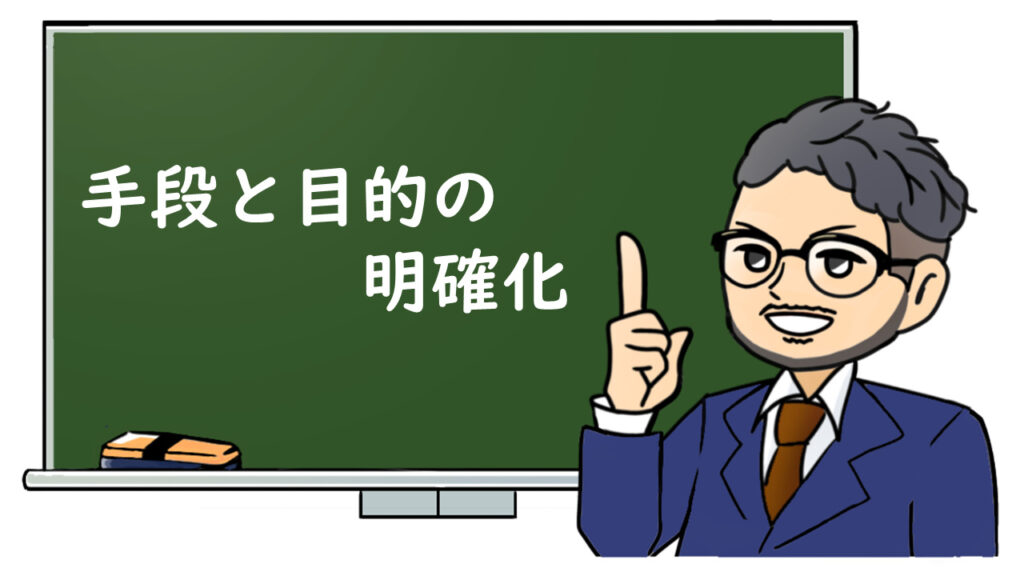
今、私たちがしていることが何なのか、何のためにしているのかを見失わないように、手段と目的を明確にしておきましょう。
たとえば、数学の『一次方程式の解き方』を学ぶのに
目的:順序立てて計画的に物事を処理し、構造的な思考を身につける
手段:等式の性質、移項を学んで、一次方程式の解き方を理解する
となります。
ですが、次のように
目的:等式の性質、移項を学んで、一次方程式の解き方を理解する
手段:全員一斉に同じ課題で、家庭での演習をする
としてしまうケースが多いです。
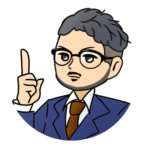
理解できている生徒はやる必要がありませんし、わからない生徒には個々に合わせた補充が必要です。
手段を目的化しないこと
おわりに
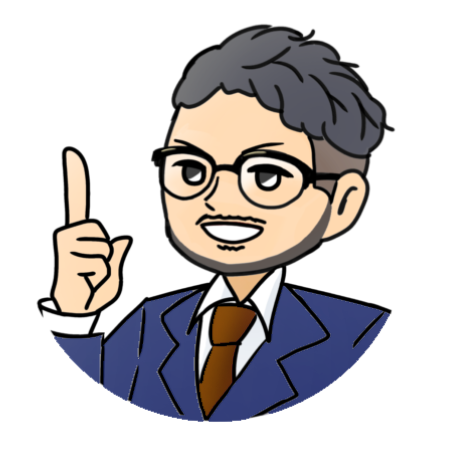
「生徒の成長を支えること」が、学校教職員の最大の使命であり職務です。
その指導や方法は、教職員の個性や経験、置かれた状況により異なります。
行うときには「効果性」「効率性」を意識しましょう。
そして、教職員にとってなくてはならない3つの視点
「感性」「スキル」「根拠」を大切にし、指導の目的はなんなのか、「手段を目的化しない」指導を心がけていきましょう。
コロナ対応等で大変な時期ですが、一緒に頑張りましょう。
春はもうすぐそこです。応援しています。
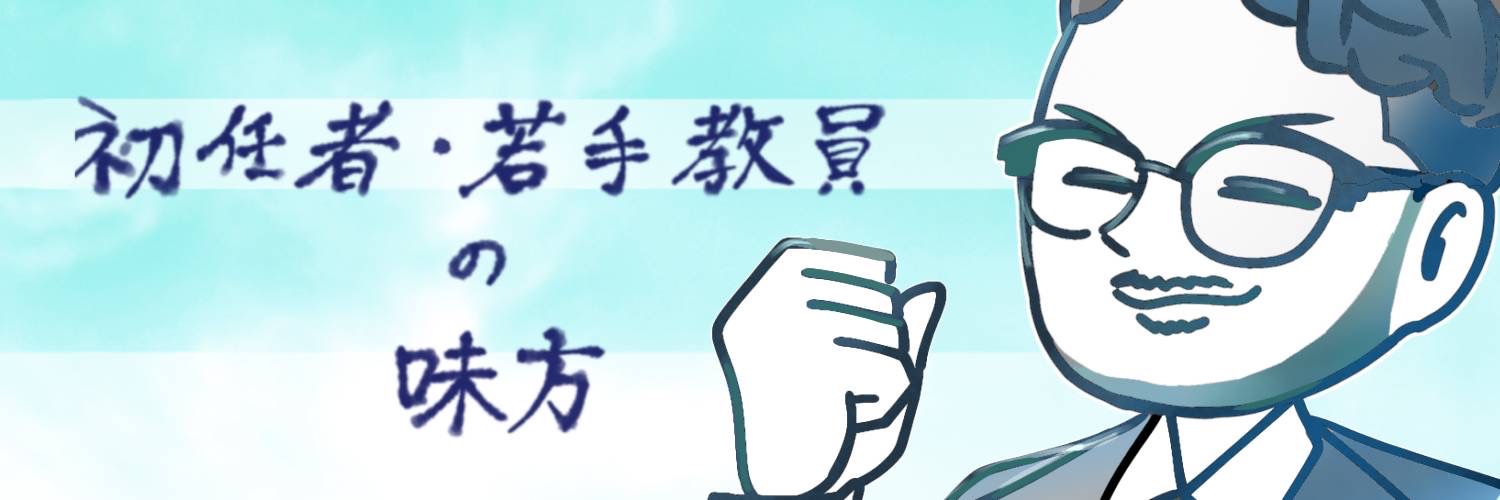



コメント