現代の学校現場には、慌ただしさが満ちている。
子どもたちは多様な課題を抱え、先生たちは限られた時間と人員の中でその一つひとつに応じながら、授業・生活指導・保護者対応に追われている。
そんな中で、僕たちはふと立ち止まり、こう自問することがある。
「教育って、なんだろう?」
「こんなに忙しくて、本当に子どもと向き合えているんだろうか?」
そんな問いに、僕は“茶道”の精神が大きなヒントを与えてくれると感じている。
茶道に流れるのは、「静けさという豊かさ」
茶道と聞くと、どこか特別な世界に思えるかもしれない。
だがその本質は、とてもシンプルだ。
静かな部屋で、湯が沸く音に耳を澄まし、一つひとつの所作を丁寧に行いながら、相手に一杯のお茶を差し出す。
そこには、「心を込める」という行為が、実に美しく、自然に表れている。
今の教室には、この「静けさ」が決定的に足りていないように思う。
静かになる=管理すること、と思われがちだが、静けさとは、内側から湧いてくるものだ。
子どもたちが「ここは安心していていい場所なんだ」と感じたとき、自然と教室の空気は整っていく。
そのためには、まず教師である僕たち自身が、自分の心を整えることが求められる。
茶道はその訓練を、日々の営みの中で実践している。
「一期一会」のまなざしを、子どもに向ける
茶道には有名な言葉がある――「一期一会」。
「今日のこの出会いは、もう二度と訪れない」という意味だ。
教師という仕事もまた、毎日がこの「一期一会」の連続である。
たとえ毎日同じ教室、同じ生徒と過ごしているように見えても、昨日と同じ日は一日もない。
昨日できなかったことが今日できた子。
今日はなぜか元気がない子。
何気ない一言が心に残る瞬間。
そういった“かけがえのない瞬間”を、僕たちはつい流してしまいがちだ。
なぜなら、忙しすぎるから。時間がないから。余裕がないから。
でも、茶道のように「今日このときだけ」を大切にする意識を持つことで、子どもとの関係は変わる。
言葉がなくても、「見てるよ」「気づいてるよ」というまなざしは伝わる。
教育とは、関係の中でしか育たないのだ。
所作が心をつくる
茶道では、道具の置き方、茶碗のまわし方、立ち座りのすべてに意味がある。
形をなぞるのではない。その一つひとつの所作が、心を調える作業なのだ。
これを教育に置き換えてみる。
- 朝の「おはようございます」を、ただ言うか、心を込めて言うか
- 黙々と掃除する時間に、物や場への感謝を感じられるか
- ノートを丁寧に書く子の姿勢を、しっかり見取れているか
こういった所作の積み重ねが、学校という場の“空気”をつくる。
そして、教師の姿勢が教室全体の雰囲気を左右する。
忙しいときほど、僕たちは動作が雑になる。
だからこそ、「丁寧に動くこと」「整った所作を意識すること」は、教師自身のセルフマネジメントにもつながる。
教師にこそ、内省する“間”が必要だ
茶道とは、ある意味「内省の儀式」だと思う。
外に向かう言葉は少なく、自分の心と向き合う時間が流れている。
教育において、内省できる教師は強い。
それは「正解がわかる」教師ではなく、「迷いながらも、自分の立ち位置を考えられる」教師のことだ。
今日の授業はうまくいったのか?
あの子の言葉に、ちゃんと向き合えただろうか?
あの保護者への返答は、誠実だったか?
こうした問いを、自分に投げかける“余白”が、教師を成長させる。
だが今の学校には、その時間がない。
だからこそ、意識的に「間」を持とうとする姿勢が、何より大切になる。
おわりに
僕は、教育に茶室をつくれと言いたいわけではない。
だが、茶道が大切にしてきた精神――静寂、丁寧、内省、一期一会――は、教育にこそ必要なものだと確信している。
教室は、子どもと教師が出会う、たった一度きりの今日の場。
だからこそ、その空間を整え、心を整え、丁寧に向き合いたい。
茶道に学びながら、僕たち自身が「教室という茶室」の亭主としての在り方を、見つめ直すときなのかもしれない。
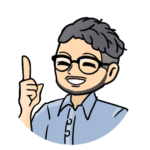
この記事が、日々の忙しさの中で少しでも「立ち止まるきっかけ」になれば嬉しいです。
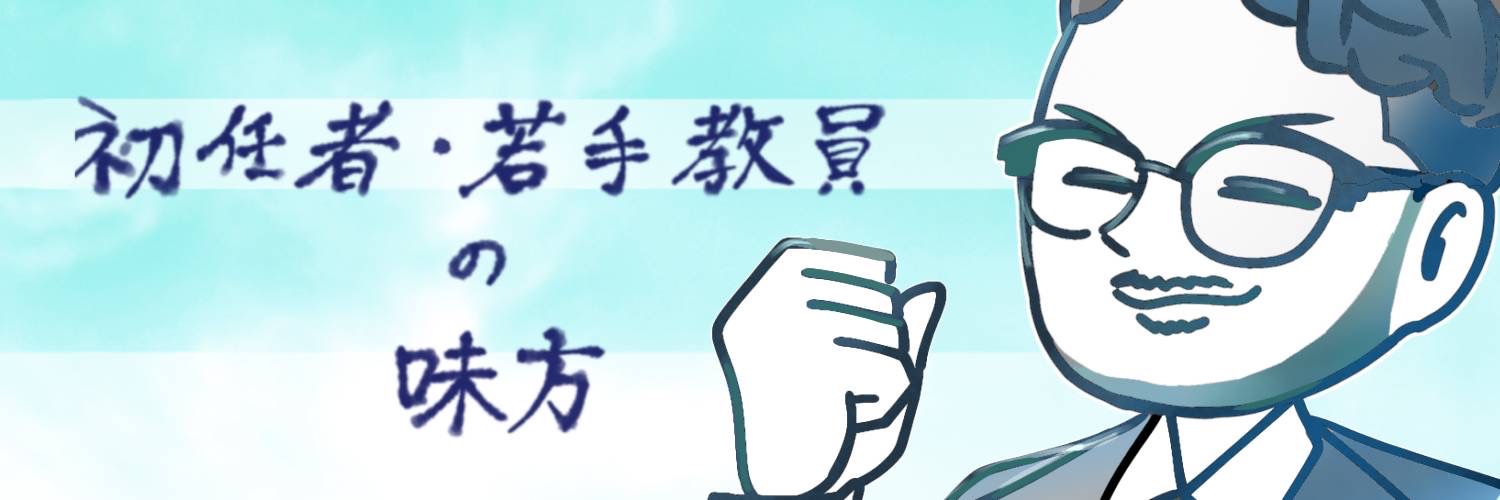
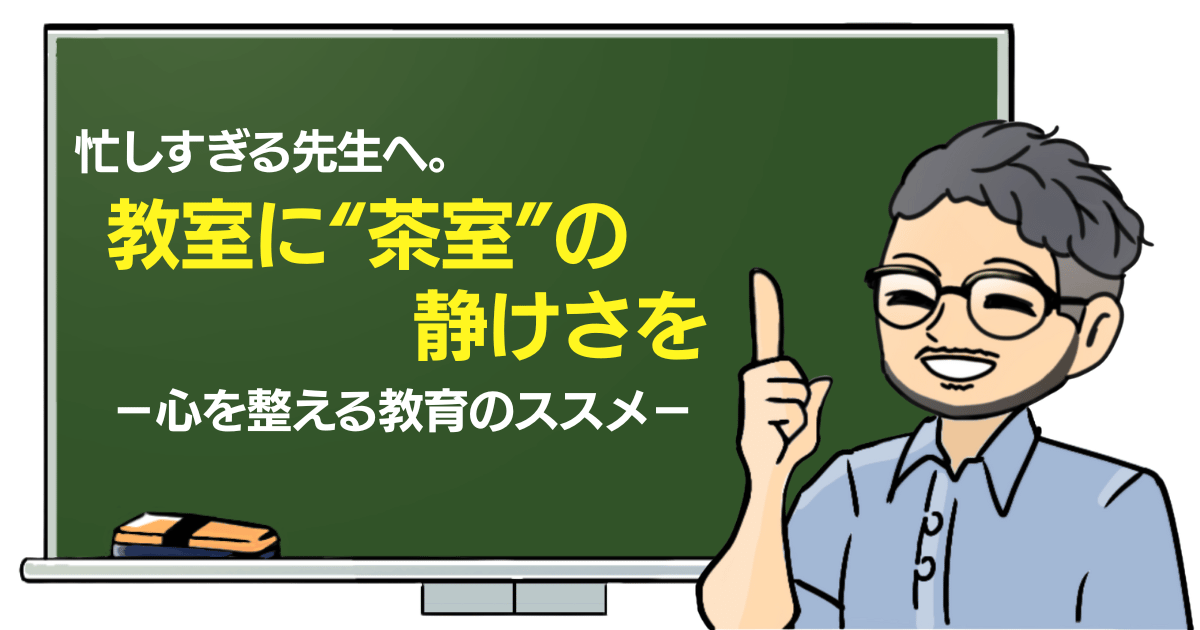


コメント