新学期が始まって3週間ほど。
授業開きも終え、学校は平常運転をしていることと思います。
さて、今回は授業の「分析と改善」についてです。
小テスト等で生徒の反応が悪ければ、「授業に問題がある」と考え、改善する必要があります。
評価をつける時期になってからだと遅いので「分析と改善」について、今から考えていきましょう。
「分析」と「対策」

授業を分析するために、指標となるのは定期テスト・小テスト・実技テスト等です。
反応率と観点別による分析と対策を考えてみましょう。
反応率による分析と対策
誤答(上手くできていない内容)の多いところを抽出して分析します。
※数学の場合だと…
【分析例】
1組は①をエと答えた誤答が多く、2組はウと答えた誤答が多かった。
だから、
「1組は演算選択の学習が不十分で、2組は演算処理の学習が不十分」
と分析できる。
これをもとに対策を考えると…
【対策例】
今後は、
問題解決の過程を説明させたり、他の方法で考えさせたりする指導にポイントをおこう。
とすることができる。
観点別による分析と対策
【分析例】
「知識・技能」は3組も4組もよくできている。
しかし、
3組は「思考力・判断力・表現力」が60%、4組は「主体的に学習に向かう態度」について70%が誤答となっている。
【対策例】
今後は出題のねらいや単元の評価基準を具体的学習活動として示し、めあてを明確にして授業を展開する。
授業改善の進め方
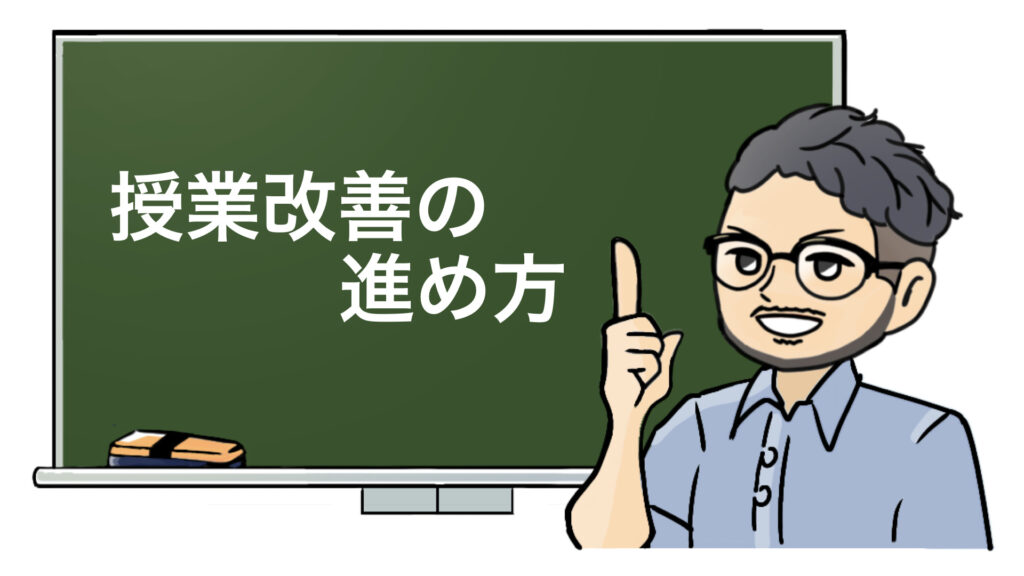
結果の分析
問題別、内容別、観点別で定期テストや小テスト、実技テスト、提出物等の結果を分析します。
正答率や誤答が多かった箇所を学年、学級、個人の視点で分析し、分布や偏りをみます。
授業の改善策を作成
指導方法の課題の分析及び今後の方針を立てます。(全体でどうするか?各学年段階でどうするか?)
そして、授業改善のための全体の計画をする。
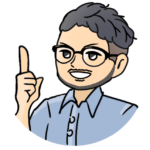
同教科が複数いる場合は、正答率や誤答率の分析について他の教員とも協議するとよいでしょう。
改善策の実践及び評価
改善策を授業実践し保護者の理解を求めます。※授業公開等で
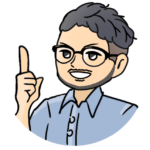
授業公開は改善策の良き発表の場であったりします。
改善策について生徒、保護者等から意見を聴取し教科内や学年等で協議します。
授業改善は、授業を受けた生徒に直接アンケートし、生徒が改善を実感しているかどうかが重要です。
生徒には、「短い言葉で、具体的にどこの内容をどうするのか」を助言しましょう。
「○○を練習します」「○○を覚えましょう」「○○の要点を整理しなさい」など、具体的かつ端的にを心がけましょう。
おわりに
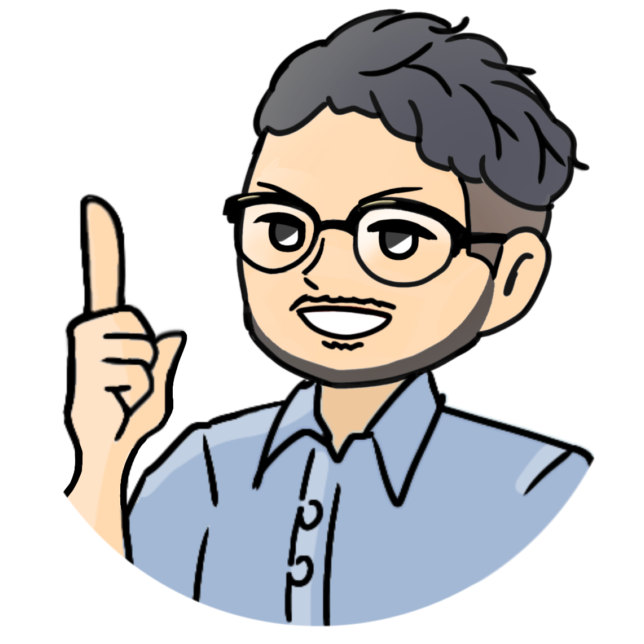
特に定期テストの分析は、時間の都合上怠ってしまうことも少なくありません。
ですが、その分析にこそ、授業改善のヒントが隠れています。
丸つけして、データ入力して返却するだけでなく、授業改善のためにも分析にも力を入れてみてください。
私たちが、まず頑張らなければならないのは「授業」です。
「分析と改善」で、授業力向上を目指していきましょう。
いろんな業務で大変な毎日ですが、一緒に頑張りましょう。
応援しています。
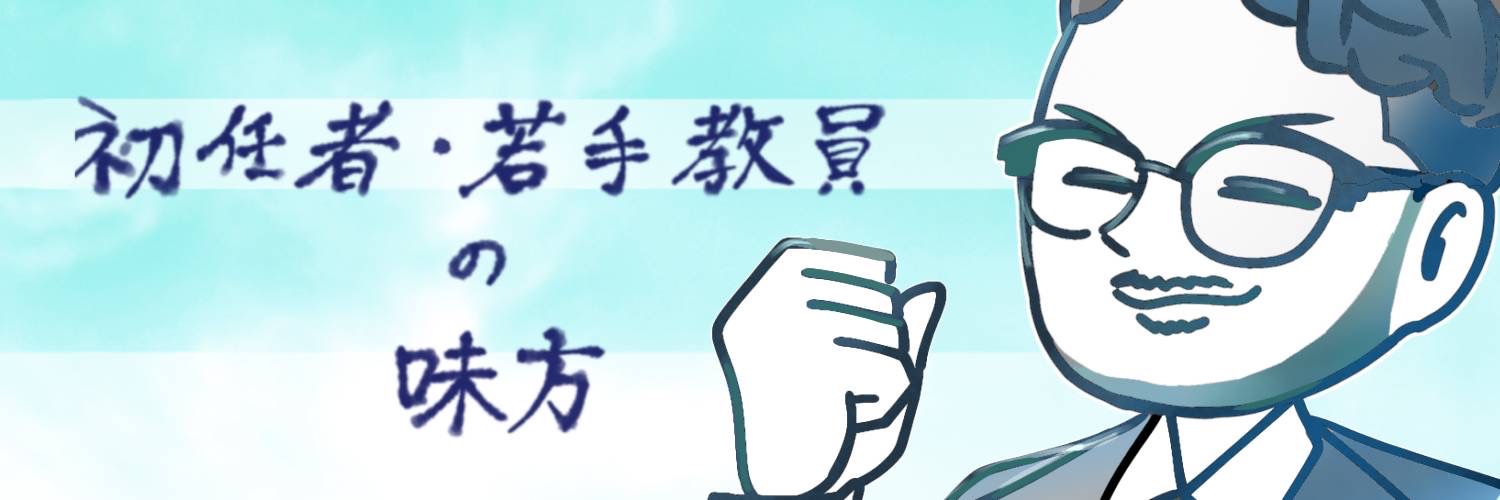



コメント