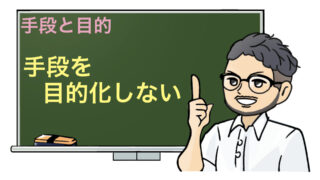 授業づくり
授業づくり 手段と目的 手段を目的化しない
さて、私たちは時どき、「この活動(学習)は何のためなのか」わからなくなることがあります。そのときは、きちんと立ち止まり、手段と目的を明確にする必要があります。今回は、数学を例に「手段と目的」についての考え方を紹介していきます。
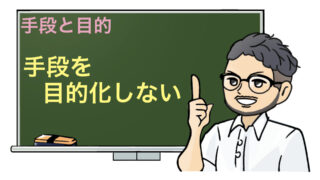 授業づくり
授業づくり 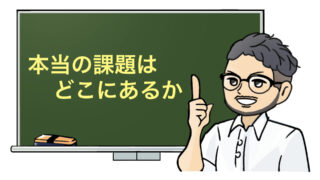 働き方
働き方 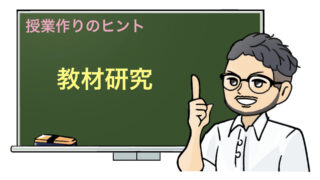 授業づくり
授業づくり 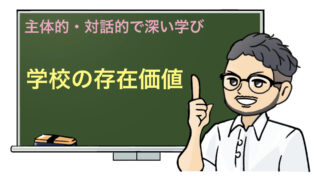 授業づくり
授業づくり 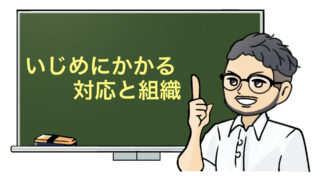 学級経営
学級経営 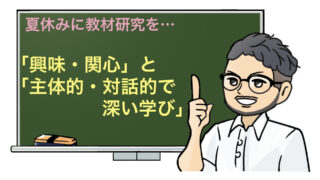 授業づくり
授業づくり  授業づくり
授業づくり 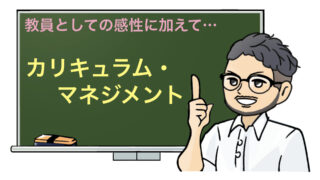 授業づくり
授業づくり 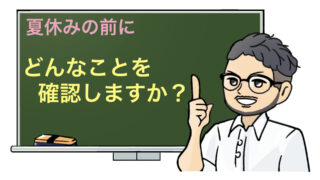 学級経営
学級経営 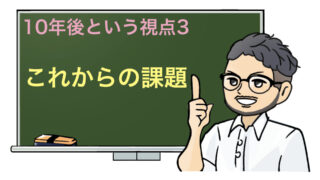 働き方
働き方