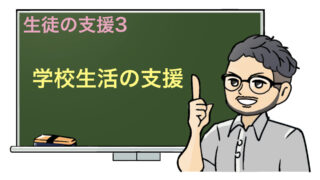 特別支援
特別支援 生徒の支援3 学校生活の支援
支援が必要な生徒の中には、学校生活を送るのが精一杯の生徒もいます。そういった生徒に対して、学校としてできる支援は何か。保護者への協力依頼など合わせて考える必要があります。今回は、学校生活での支援の方法を考えていきましょう。
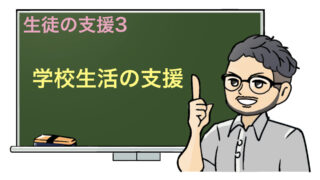 特別支援
特別支援 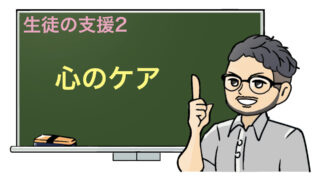 特別支援
特別支援 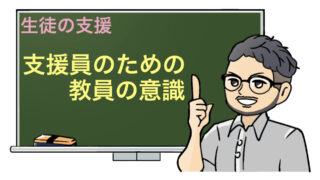 特別支援
特別支援  学級経営
学級経営 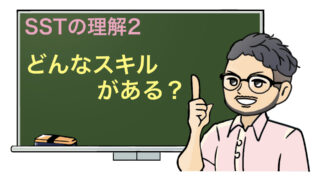 学級経営
学級経営  学級経営
学級経営  特別支援
特別支援 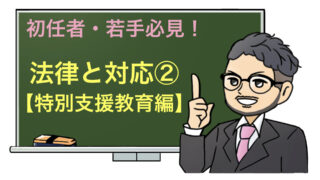 特別支援
特別支援 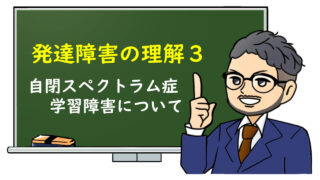 特別支援
特別支援 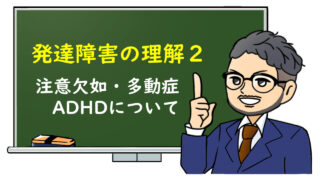 特別支援
特別支援