学習の評価をするにあたって、「評価の基準」を明確にしておく必要があります。
授業開きの際に、事前に生徒に伝えておくことがベストですが、レポートやノート提出の際に確認しておくと良いでしょう。
また、説明を求められたら、明確な返答ができるように評価の基準は用意しておきましょう。
レポートやノート等の提出物
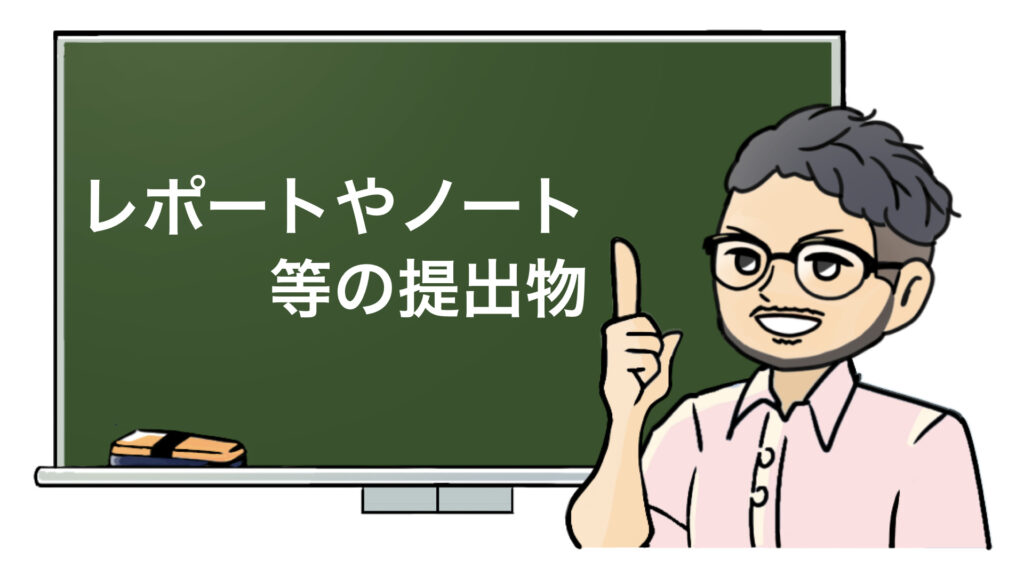
単純にA・B・C・Dと付けるのではなく、なぜB(A・C・D)なのか基準を明確にしておくことが必要です。
たとえば数学のレポートの観点なら
内容
水準を大幅に超えている…A
おおむね水準を満たしている…B
やや不十分である…C
内容がない、もしくは大きくかけ離れている…D
表現の明快さ
非常にわかりやすい…A
わかりやすい…B
ややわかりにくい…C
わかりにくい、もしくは書かれていない…D
自己評価・感想
理解が大きく深まっている…A
理解が深まっている…B
理解の深まりが不十分である…C
理解できていない、もしくは書かれていない…D
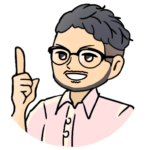
これらを総合して、BBAなら「B」、といった具合に評価します。
未提出については、レポートが白紙で提出されたものとして評価します。
この例では、レポートの総合評価は「B」ですが、
「内容」は「知識・理解」の観点
「表現の明快さ」は「思考力・判断力・表現力」の観点
「自己理解・感想」は「主体的に学習に取り組む態度」の観点
の評価とします。
たとえば数学のノートの観点なら
内容
授業の内容を大幅に超えている…A
授業の内容を上回っている…B
授業の内容・板書程度…C
不十分、もしくは書かれていない…D
表現の明快さ
非常にわかりやすい…A
わかりやすい…B
ややわかりにくい…C
わかりにくい、もしくは書かれていない…D
自己・家庭学習
非常によく取り組んでいる…A
よく取り組んでいる…B
やや取り組みが不十分である…C
あまり、もしくはほとんど取り組めていない…D
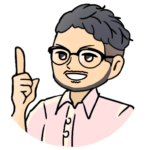
これらを総合して、BCCなら「C」といった具合に評価します。
未提出については、ノートが未記入で提出されたものとして評価します。
この例では、ノートの総合評価は「C」ですが、
「内容」は「知識・理解」の観点
「表現の明快さ」は「思考力・表現力・判断力」の観点
「自己・家庭学習」は「主体的に学習に取り組む態度」の観点
の評価とします。
協働的な活動(話し合い活動)
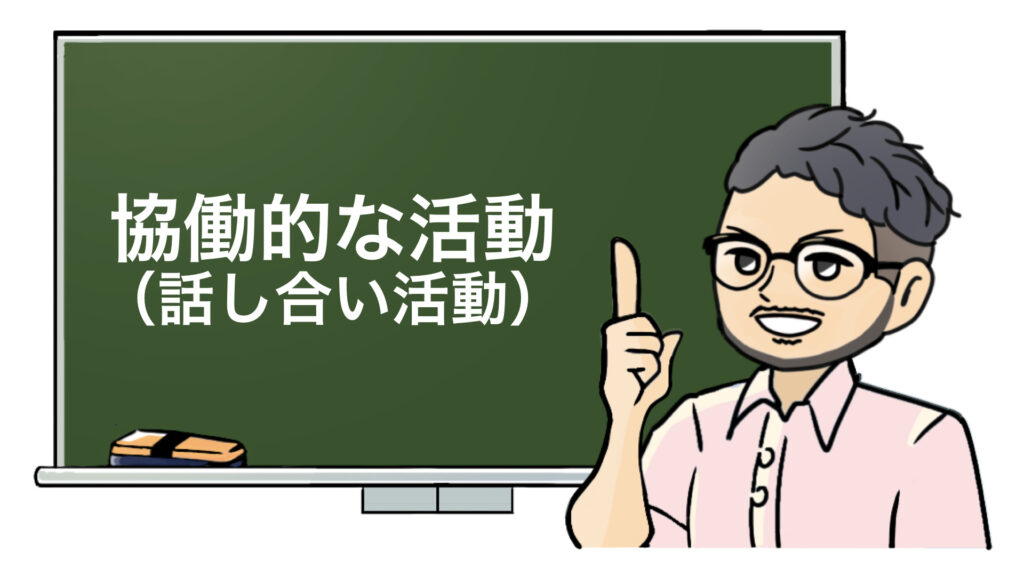
数学におけるグループ討議
他者との恊働
他者の意見を尊重しながら自分の意見を根拠に基づき論理的に伝える…A
他者の意見を尊重しながら自分の意見を伝える…B
自分の意見を伝える、もしくは自分の意見を持ってはいるが意見としては伝えていない…C
自分の意見を持たず、自分の意見を伝えない…D
思考の方向性
適切な方向性で話し合いができるよう意見を述べ、必要な試行錯誤を行っている…A
適切な方向性の話し合いの中で、必要な試行錯誤を行なっている…B
方向性の損なわれる意見が時折ある、もしくは話し合いへの参加が不十分である…C
方向性が損なわれる意見を言うことが多い、もしくは話し合いに参加しない…D
表現の明快さ
非常にわかりやすい…A
わかりやすい…B
ややわかりにくい…C
わかりにくい、まったく発言しない…D
討議活動の記録
他者の意見を理解し、自分の意見を根拠に基づき論理的に伝えることができた…A
他者の意見を尊重しながら自分の意見を伝えることができた…B
自分の意見を伝えられた、もしくは自分の意見を持ってはいるが伝えられなかった…C
自分の意見を持たず、自分の意見を伝えなかった…D
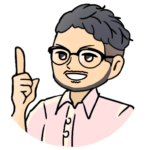
これらを総合してBCBAなら「B」、といった具合に評価します。
欠席者については、これまでのグループ討議の評価から推測して評価します。
この例では、グループ討議の総合評価は「B」ですが、
「他者との協働」は「主体的に学習に取り組む態度」の観点
「思考の方向性」「表現の明快さ」は「思考力・表現力・判断力」の観点
「討議活動の記録」は「知識・理解」の観点
の評価とします。
おわりに
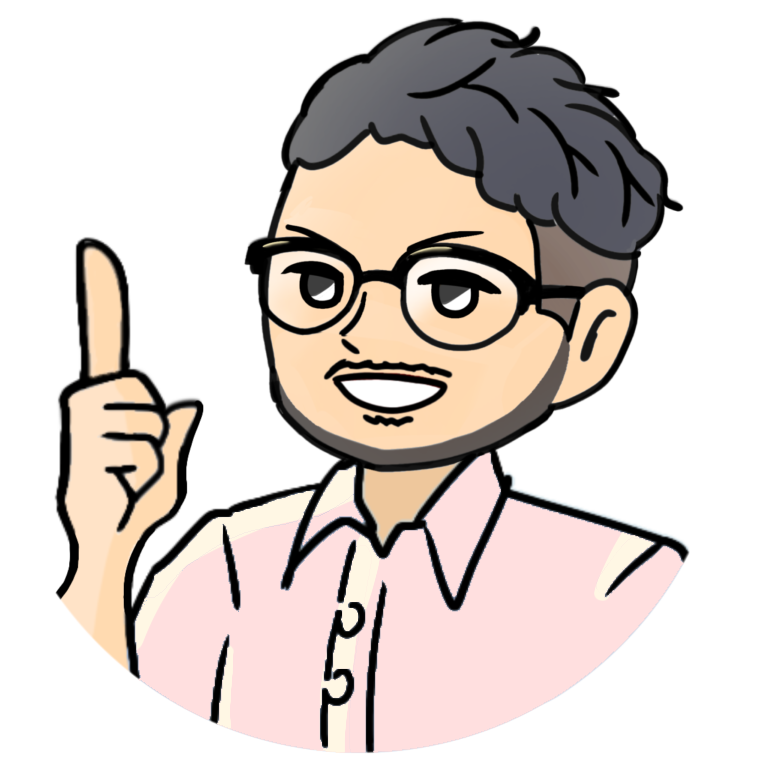
いずれにせよ、論述やレポートの作成、発表、グループでの話し合い、作品の制作等と言った多様な活動に取り組ませるパフォーマンス評価をしなければ適切な評価が行えません。
そのため、授業の組み立て、評価すべき事柄を明確にしておきましょう。
ペーパーテストの結果にとどまらない、多面的な評価が求められます。
総括的な評価に加え、個々の学びの多様性に合わせて、学習の過程における形成的な評価を行い、生徒の資質・能力がどう伸びているか、日々の記録やポートフォリオなどを通じて生徒自身が把握できるようにしましょう。
これから雨が続きます。
暑くてジメジメするのはしんどいですが、一緒に頑張りましょう。
応援しています。
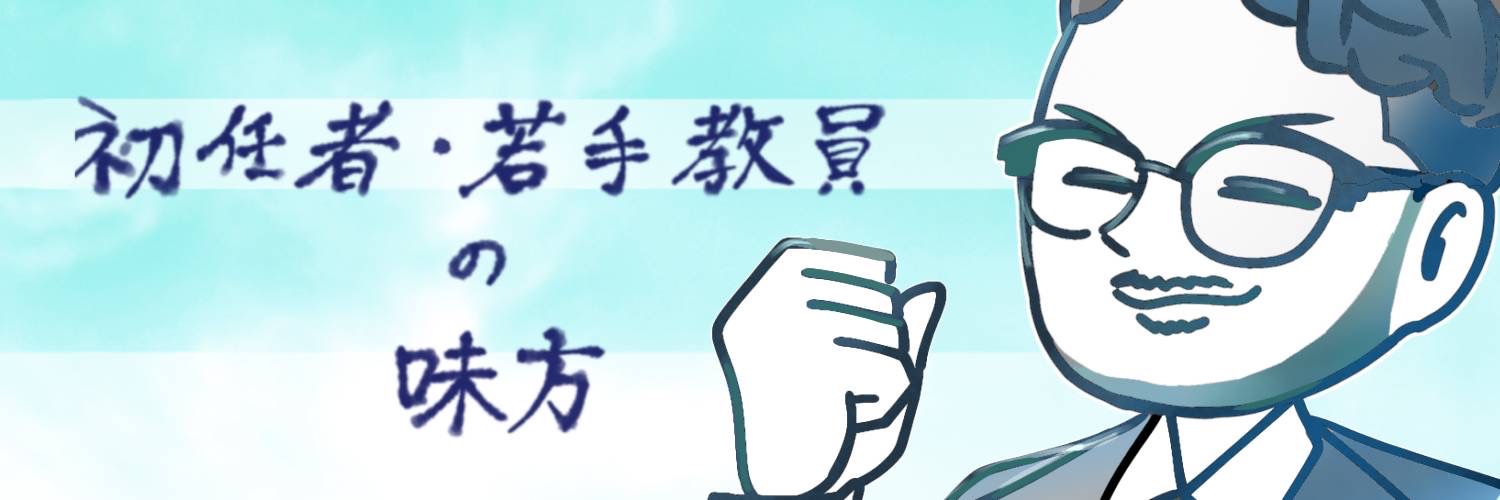
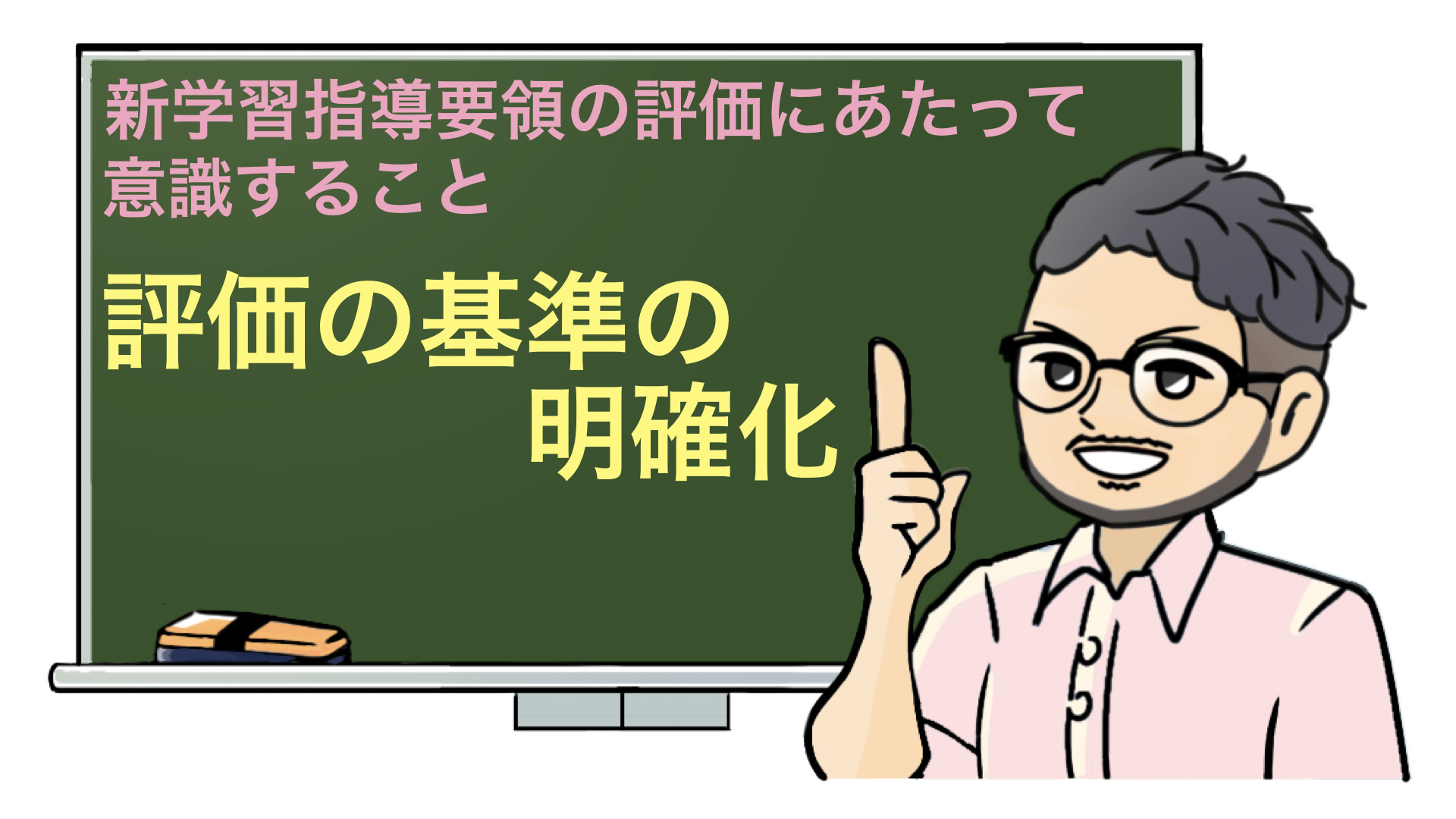


コメント