今日は前回のテーマに引き続き、「生活指導での生徒からの聞き取り」についてです。
前回記事が未読の方は、こちらもご覧ください。
今回は、生活指導後の「保護者連絡」の仕方です。
生活指導があった場合、必ず保護者連絡をします。
特に、初任者・若手教員はどうすれば良いか、悩むところだと思いますので、一緒に確認していきましょう。
連絡する前に…
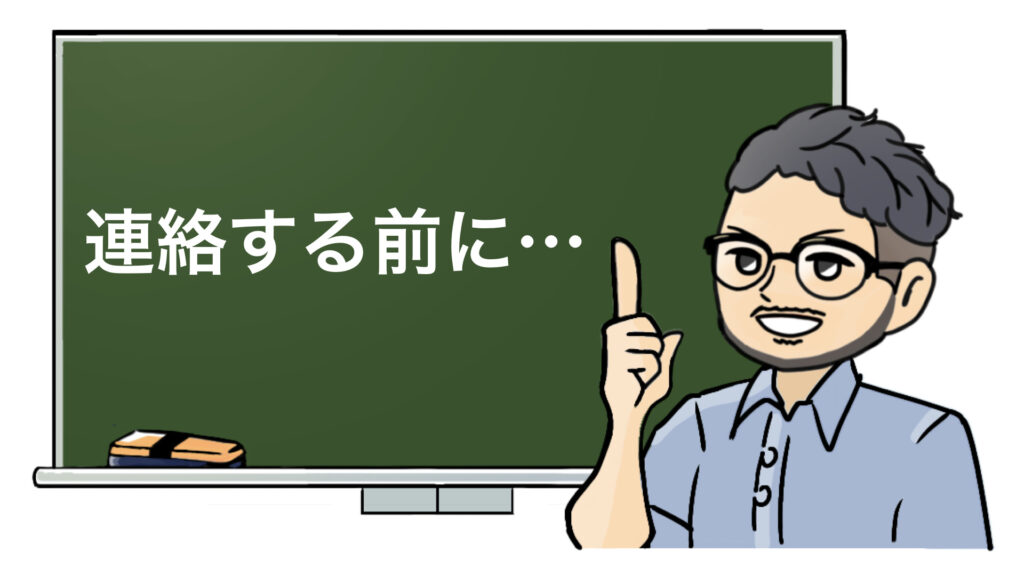
事実確認
まずは事実確認をしましょう。
当該児童・生徒に聞き取りを行います。
聞き取りはできるだけ丁寧に行いましょう。
「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どのように」「誰と」「したか」
時系列に沿って記録をまとめます。
そのときの教員の人数にもよりますが、原則複数対応です。
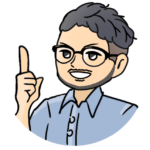
「聞き役」と「記録役」です。
「言った、言ってない」が起こらないようにするのにも有効です。
情報共有
学年や関係職員、学校全体で情報共有します。
そして、生活指導主任に報告し、管理職にも報告しましょう。
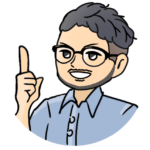
情報に大小は関係なく、些細なことも報告することが大切です。
保護者との連絡で…
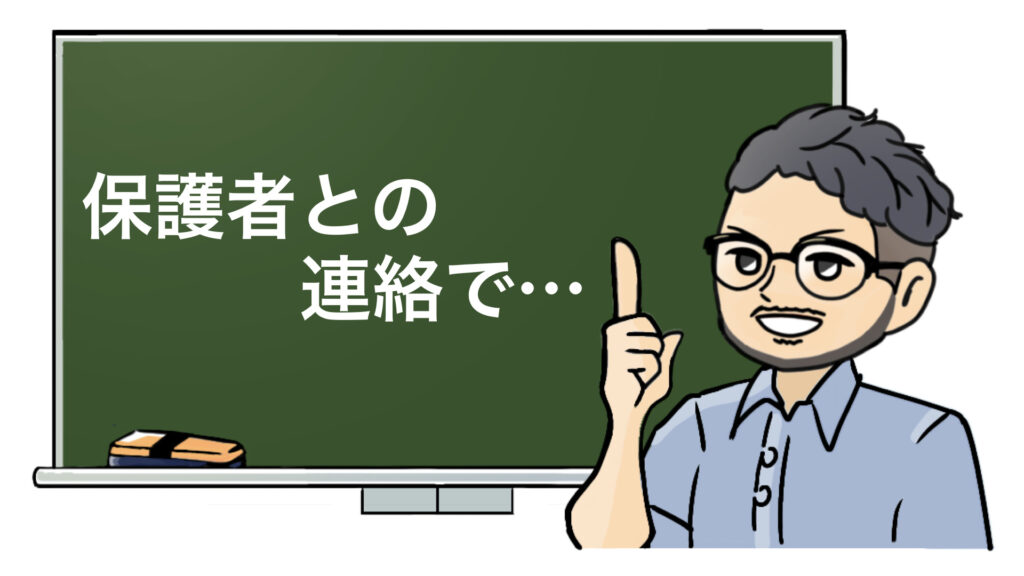
事実確認
「いつ・どこで・誰が・何を・どのように・誰と・したか」を「簡潔に・丁寧に」説明します。
「こんな些細なことで連絡して!」と言われることがあります。
これは「うざったい」と思っているだけで、信頼感を損なうことではありません。
ですが、次のように言われる場合は危険信号です。
「なぜ早く連絡しなかったのか!」
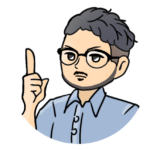
これは、担任、学年、学校への不信感に直結します。
そのため、保護者連絡は「早めに・こまめに」行います。
関係生徒の個人情報には十分注意してください。
また、学校・教員側の対応の不備がある場合は、丁重に謝罪をします。
「加害者」対「被害者」(謝罪等)
【被害者への謝罪】
被害者生徒が「謝罪はいらない」と言っても保護者に必ず確認をします。
加害者側がごねて謝罪しない場合は、その旨を丁重に伝えます。
物品破損・盗難・ケガ等では、「金銭的な対応」も依頼します。
保護者との話し合い
建設的に、子供を中心に話します。
「共感しても、同意はしない」ことです。
加害者側・被害者側に立ってしまうと、問題を拗らせる原因になります。
おわりに
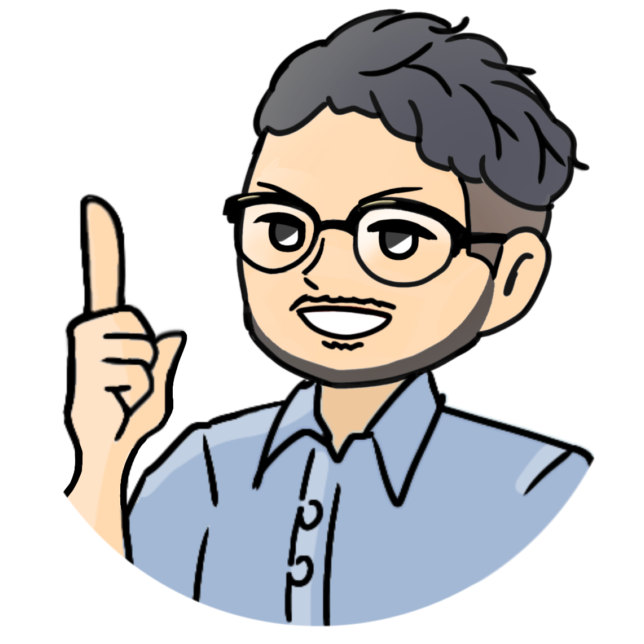
保護者連絡のポイントは「確実に内容が伝わる」「学校の真意を伝える」「明確に対応する」の3つです。
そして、私たち教員は「あくまでも中立」です。
生徒の健全育成の立場で接するように心がけましょう。
5月も終盤、1学期も折り返しです。
大変な毎日ですが、一緒に頑張りましょう。
応援しています。
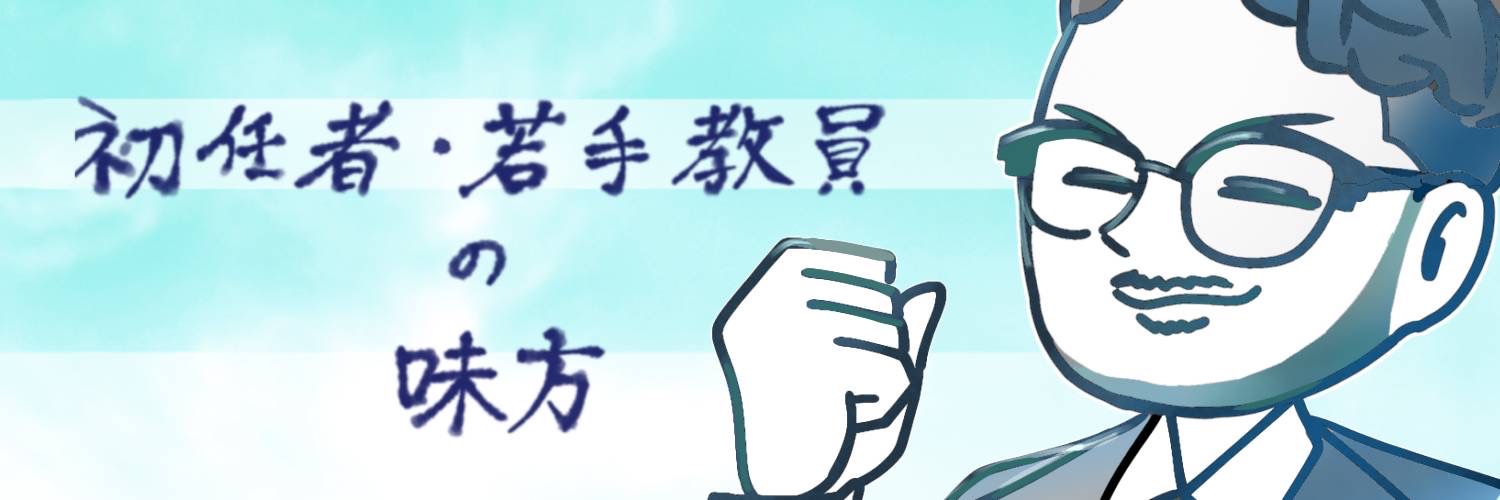
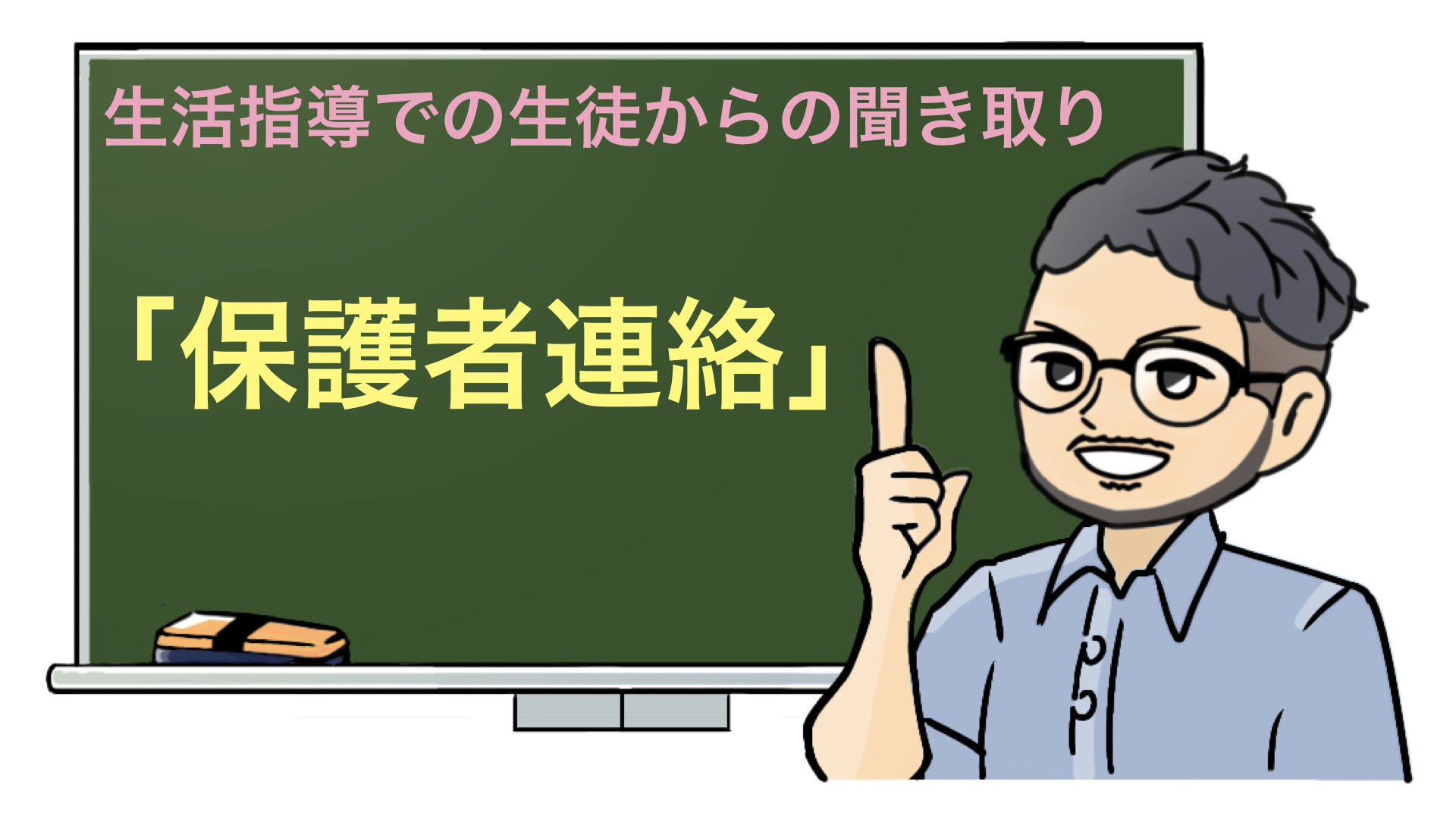

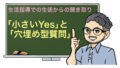

コメント