「なんでも聞いてね」が、なぜこんなにプレッシャーなのか
「わからないことがあったら、なんでも聞いてね」
そう声をかけてもらったこと、ある人も多いと思います。
僕も、初任のころに何度も言われました。
けれど、なんででしょう。
この言葉が逆に、苦しくなってしまう。プレッシャーになる。
本当はありがたいはずなのに、素直に甘えられない。
そんな風に感じた経験、ありませんか?
「わからないことが、わからない」問題
初任1年目の春。
右も左もわからないまま、担任として走り出します。
目の前には、学級開き、名簿整理、教科書、道徳の準備、係や当番、給食の流れ、保護者からの連絡、学年会、会議、提出物、記録…
次から次へと「これもやっといてね」が舞い込んでくる。
「これって、どうすればいいんですか?」と聞こうとしても、
そもそも“どこが分からないのかが分からない”状態。
そんなときに「なんでも聞いてね」なんて言われても、
「何をどう聞けばいいのか」すら分からない。
「先輩の貴重な時間を奪ってまで、自分なんかが聞いてもいいのかな…」
「質問するたびに『また?』って思われたら嫌だな…」
こうして、誰にも頼れなくなっていきます。
動いても怒られ、止まっても叱られる
ようやく少し慣れてきたなと思って、自分なりに動いてみたら――
「勝手にやる前に、まず確認してよ」と怒られる。
じゃあ、次は指示を待ってみた。すると――
「言われるまで動かないの?もっと自分から考えて」と叱られる。
どっちにしても、怒られる。
「どうすれば正解なのか」なんて、誰も教えてくれない。
ただただ、“空気を読めること”だけが求められる。
気づけば、職員室の片隅で、
「今年の初任、ちょっと頼りないよね」
なんて陰口が聞こえてきたりする。
何をしても正解がない世界で、
自分の価値だけが、どんどん削れていく。
研修は“現場の助け”にならない
そんな中で迎える、初任者研修。
「やっと何か学べるのか」と期待するけど、
始まってみると、引退校長先生の思い出話。
「私の若い頃はね…」って。
いや、今の僕らの話をしてくれ…って思う。
指導主事の事例検討も、現場のドロドロしたリアルからはかけ離れていて、
「そんなんじゃないんだよな…」ってなる。
本当は知りたいんです。
- 子どもとの距離の詰め方
- 保護者からクレームが来たときの対応
- 隣のベテランの先生とうまくやっていくコツ
- 学級を崩壊させないために、何を大事にしたらいいのか
けれど、研修ではそういう話はほとんど出てこない。
結果的に、「学校を離れて一息つけるオアシス」か、
「通信を書くための内職タイム」になってしまう。
“心が折れる”日々
学校に戻ると、現実が待っています。
「◯◯くんと△△ちゃんがケンカしてる。至急対応して」
「保護者から連絡あり。今日中に折り返して」
「会議の資料、明日の朝までにお願いね」
「ちなみに、来週の行事はあなたがチーフね」
目が回るほど仕事があるのに、授業の準備すらままならない。
家に帰っても、仕事が終わらない。
寝落ちした深夜、ふと目を覚まして、「あ、あれ提出してない…」と焦る。
そして聞こえてくるのは――
「うちのクラスの担任、ハズレだね」
それでも、自分なりにがんばっているつもりなのに。
どうしてこんなに報われないんだろう。
それでも、伝えたい
でもね。
僕は言いたいんです。
あなたは、よくやってるよ。
つらいのは、あなたが「本気でがんばっている証拠」。
逃げずに、子どもたちと、保護者と、職員室と、ちゃんと向き合ってきたからこそ、今がしんどいんです。
今感じているのは、あなたの心が弱いからじゃない。
この構造自体が、若手にとって“無理ゲー”だから。
明日へ、続く話
この連載では、
この「無理ゲー」をどう生き延びるか、
どうやって自分を守るか、
少しでも心をラクにするにはどうしたらいいか――
そんなことを、あと2日間にわたって書いていきます。
次回のテーマは、
「正論は、時に自滅を生む。では、どう動けばいいのか?」
自分を責めてしまっているあなたへ、
少しでも、言葉が届きますように。
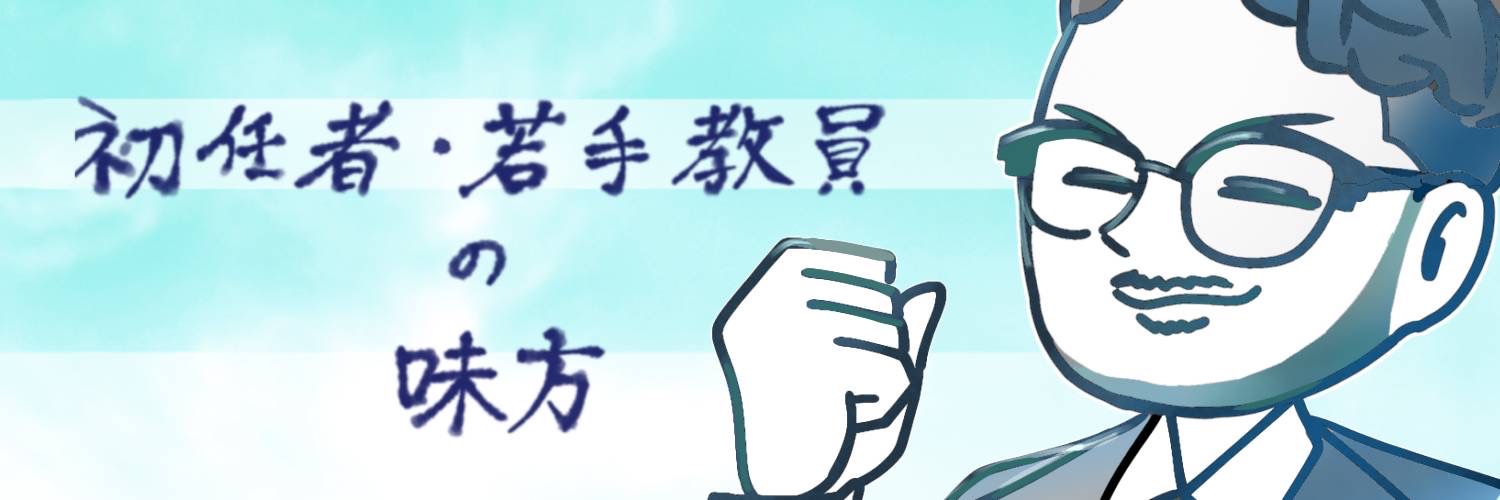
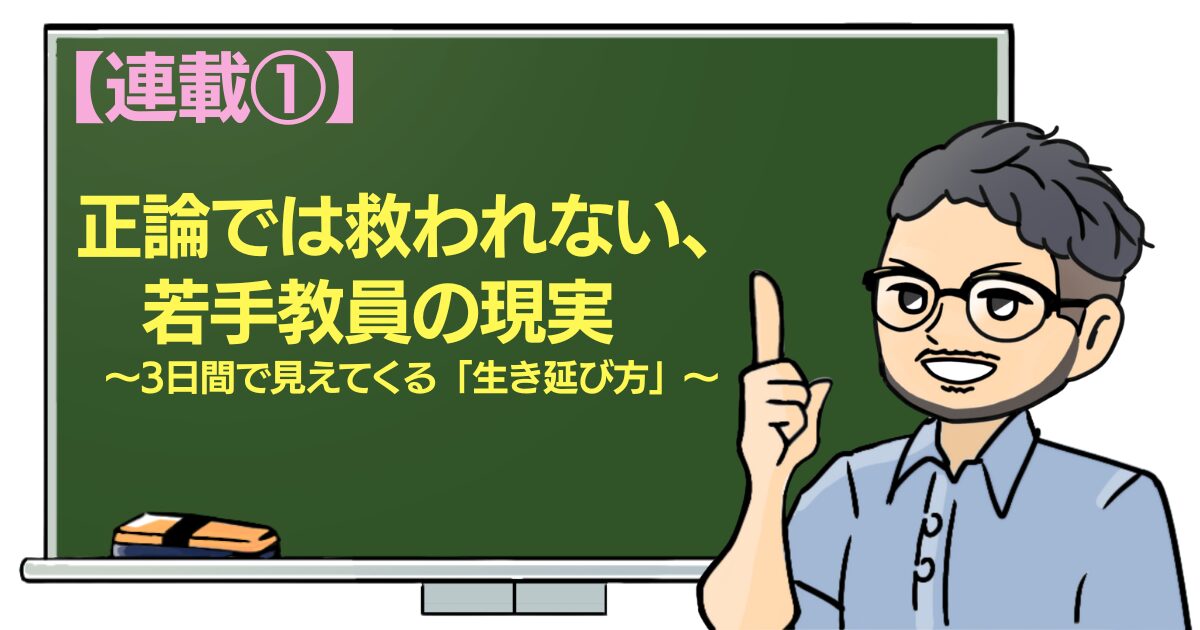


コメント