 働き方
働き方 教育本の紹介
僕自身、若手の頃は本屋に入り浸って、教育関連の本を読み漁っていたことがありました。しかし、その頃読んでいた本は「学級経営」とか「数学指導」など、自分のクラスや教科のことしか頭にありませんでした。実際に現場に出てみるとわかるのですが、教員の役目は何もクラスや教科指導だけではありません。幅広い知識と教養が求められる職業だと思っています。今回は、いくつか本を紹介します。本屋に立ち寄った際は、一度手に取って見てはいかがでしょうか。
 働き方
働き方 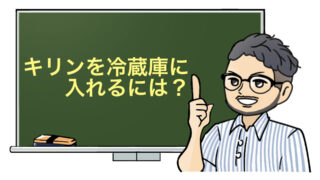 働き方
働き方  働き方
働き方 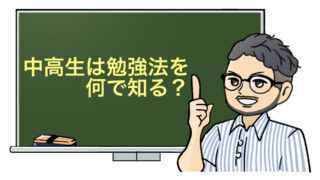 働き方
働き方 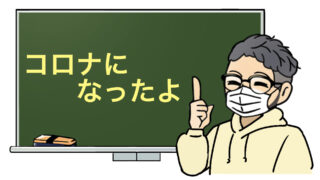 雑談
雑談  働き方
働き方  働き方
働き方  学級経営
学級経営 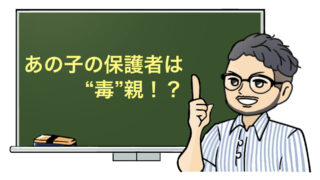 生活指導
生活指導  学級経営
学級経営