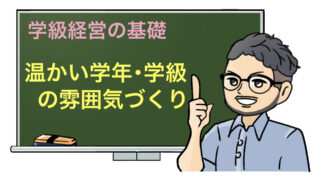 学級経営
学級経営 学級経営の基礎 温かい学年・学級の雰囲気づくり
新学期が始まって3週間、生徒も少しずつ学校に慣れてきたことと思います。クラス写真撮影や保護者会、春の健診など様々な行事も終わったところでしょうか。さて、今回のテーマは「温かい学年・学級の雰囲気づくり」です。温かい雰囲気づくりに欠かせない4つポイントを紹介します。
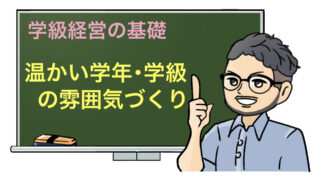 学級経営
学級経営 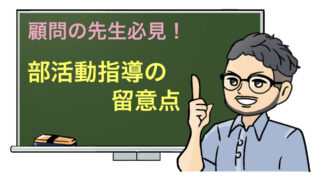 生活指導
生活指導 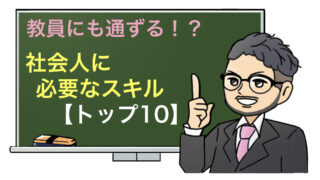 働き方
働き方 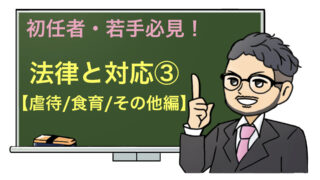 生活指導
生活指導 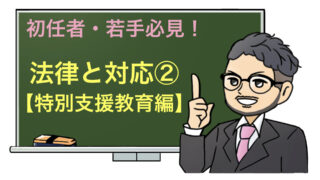 特別支援
特別支援 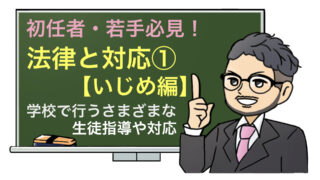 生活指導
生活指導 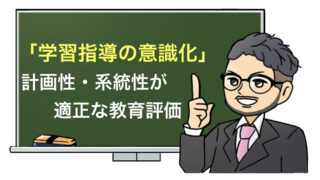 授業づくり
授業づくり 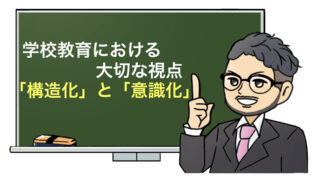 学級経営
学級経営 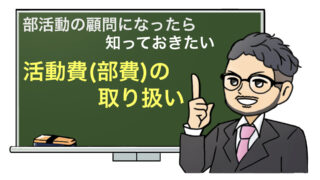 働き方
働き方 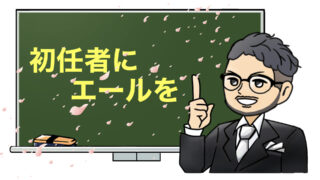 働き方
働き方