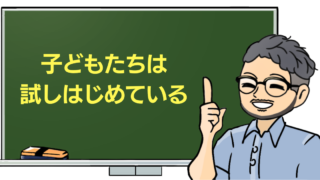 学級経営
学級経営 「今、子どもたちは先生を試し始めている」
――新学期3日目から始まる本当の学級づくり新学期が始まって、今日で3日。少しずつ子どもたちも学校の雰囲気に慣れてきて、教室の中に笑顔や会話が増えてくる頃かもしれません。でも、ここからが本当の学級経営のスタートです。よく「黄金の三日間」という...
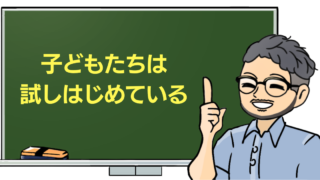 学級経営
学級経営 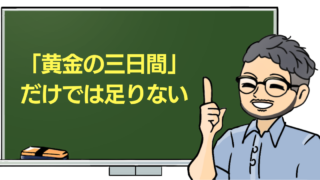 学級経営
学級経営 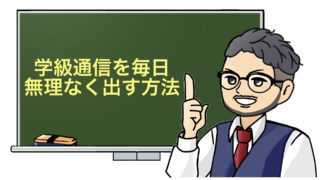 学級経営
学級経営 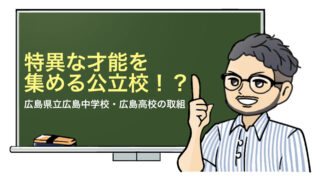 学級経営
学級経営  学級経営
学級経営  学級経営
学級経営 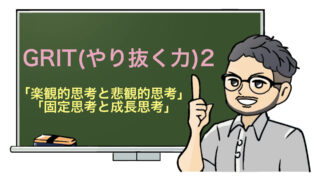 学級経営
学級経営 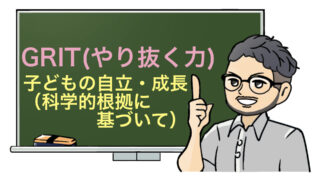 学級経営
学級経営  学級経営
学級経営 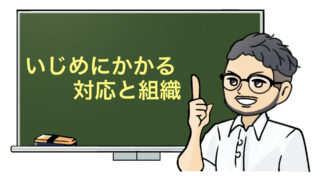 学級経営
学級経営