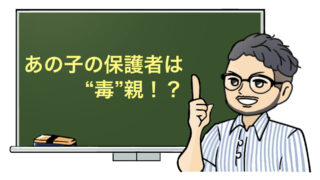 生活指導
生活指導 あの子の保護者は“毒”親!?
近年、学校生活の中で、どうにも他との交流や生活の改善ができない者がいます。その子たちは短・中期的に頑張り続けられないという特徴があります。「すぐに弱音を吐く」「健康・精神状態が不安定」「時にして自傷行為をする」などといった傾向が見て取れます。そして、こういった子の裏には「毒親」の存在がある場合が多いです。これらの親(毒親)にはどんな特徴があるのか、その対応も含め紹介していきたいと思います。
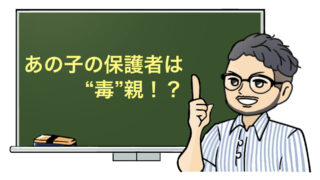 生活指導
生活指導 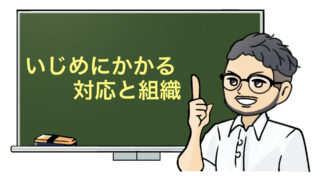 学級経営
学級経営 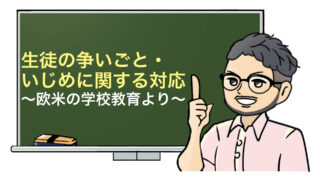 生活指導
生活指導  生活指導
生活指導 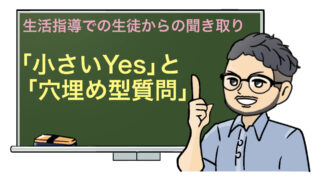 生活指導
生活指導  生活指導
生活指導 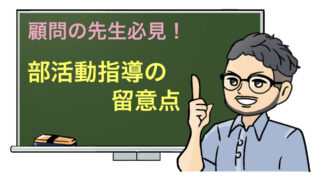 生活指導
生活指導 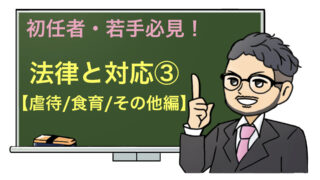 生活指導
生活指導 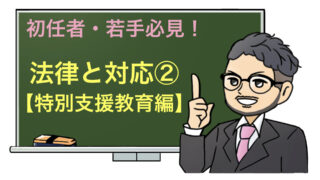 特別支援
特別支援 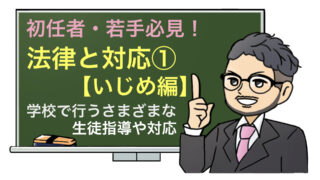 生活指導
生活指導