前回は「協働」や「協調」について、考えました。
今回は、大学入試共通テストや授業等で求められる方向性について一緒に考えていきましょう。
大学入試共通テストの改革
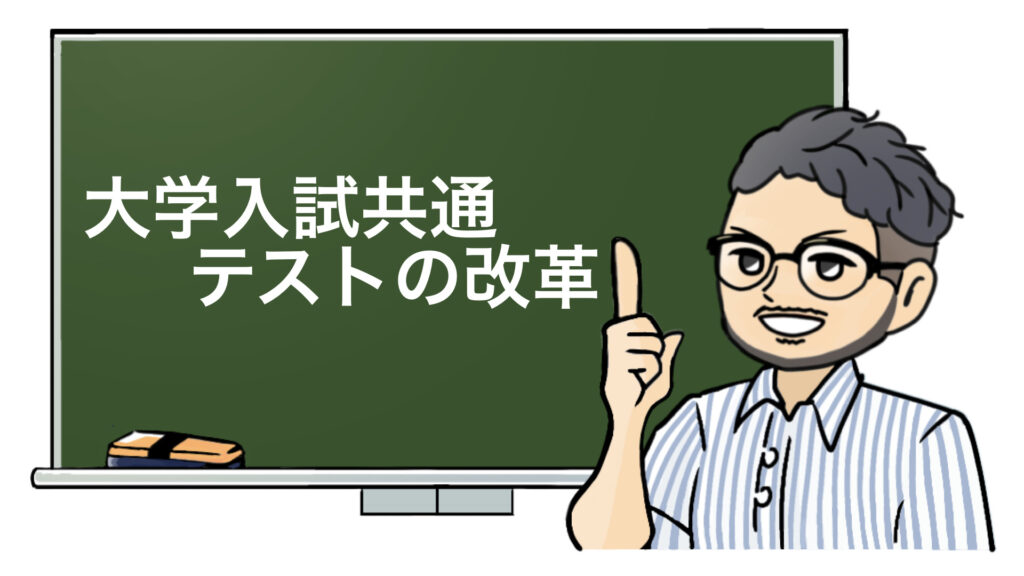
一昨年度から大学入試共通テスト改革が実施されました。
大学入試共通テスト改訂の方向性は、高校の新学習指導要領の改訂に伴う変更ですが、問われる問題の内容や方針は、PISAの「協働問題解決能力調査」問題と同質のものです。
試問の解説には、中教審「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善及び必要な方策等について(答申)」が引用され、幼稚園・小学校時期から「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体的に取り組む態度」を育成することが必要、と改めて協調されています。
大学入試共通テストの改革も、中学校(小学校・特別支援学校・特別支援学級)と無縁ではないのです。
授業等で求められる方向性
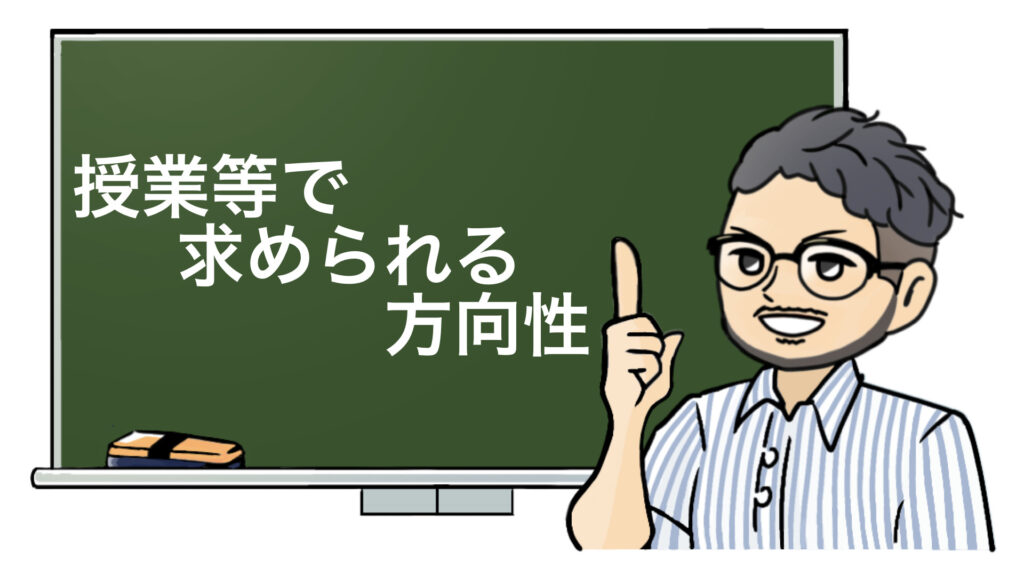
新しい学習指導要領は…
小学校・高等学校は「大改訂」でした。
内容どころか、教科名の変更、教科の統廃合・新設も大幅にあります。
これに比べ、中学校では指導内容は、ごく一部の変更にとどまります。
そのため、中学校では改訂の実感が薄いのですが…
教員の指導の仕方に言及している点では、小学校・高等学校と一緒です。
少し評価の観点が変わるだけ、なんて思っていたら大間違いです。
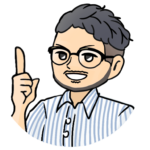
指導の仕方に言及した、という点では「大改訂」という意識を持っておきましょう。
すべての時間を「協働的なもの」にする必要はありません。
ただし、「協働的なもの」にできる授業は「協働的に」
そのときは「いかにして解決するか」を大切に…
「主体的な学び」の視点
・自分から学びに向かうにはどうするか。
・自分の意見を、どのようにして持たせるか。
・自分の意見を発表する勇気を、どう育てるか。
「対話的な学び」の視点
・異質の意見や対立の意見に、どのように反応するか。
・異質の意見や対立の意見を、どのように「協働的に」結論に結びつけるか。
・「意見の対立」を「感情的な対立」にしないためにどうするか。
・「平行線の意見」をどのように処理するか。
・「自分の責任」と「他人の責任」の範囲を、いかに確認させるか。
・自分の意見への責任を、どのように意識させ、取らせるか。
「深い学び」の視点
・自分の意見の根拠となる事柄や論理性を、どのように育むか。
・自分がどのように考えればよいかを、どのように理解させるか。
・何を考えればよいかを、どのようにして明確にさせるか。
おわりに
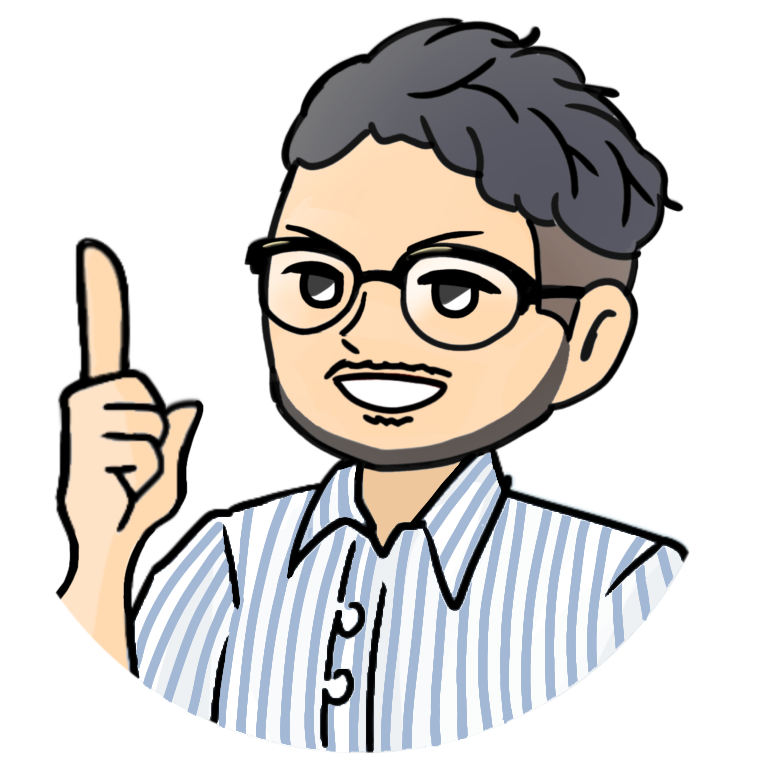
こういった視点で授業改善が必要です。
大学入試改革やPISAの「協同問題解決能力調査」のような調査にも直結します。
最終的には、小学校卒業後、上級学校で育む力の準備にしましょう。
2学期が始まりました。
大変な毎日ですが一緒に頑張りましょう。
応援しています。
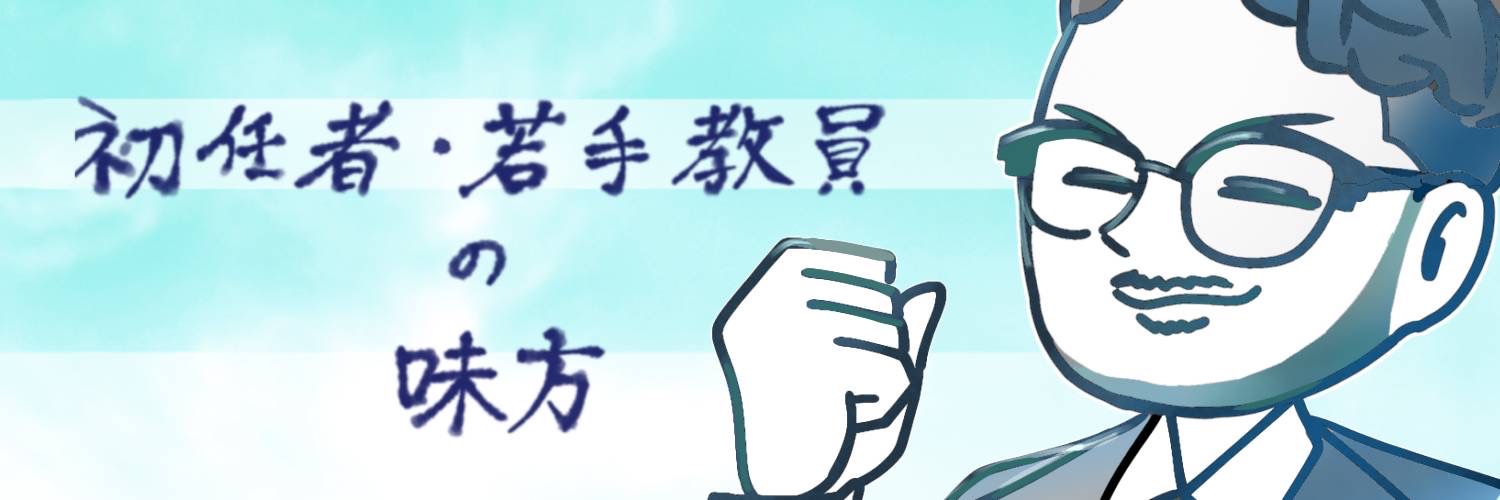
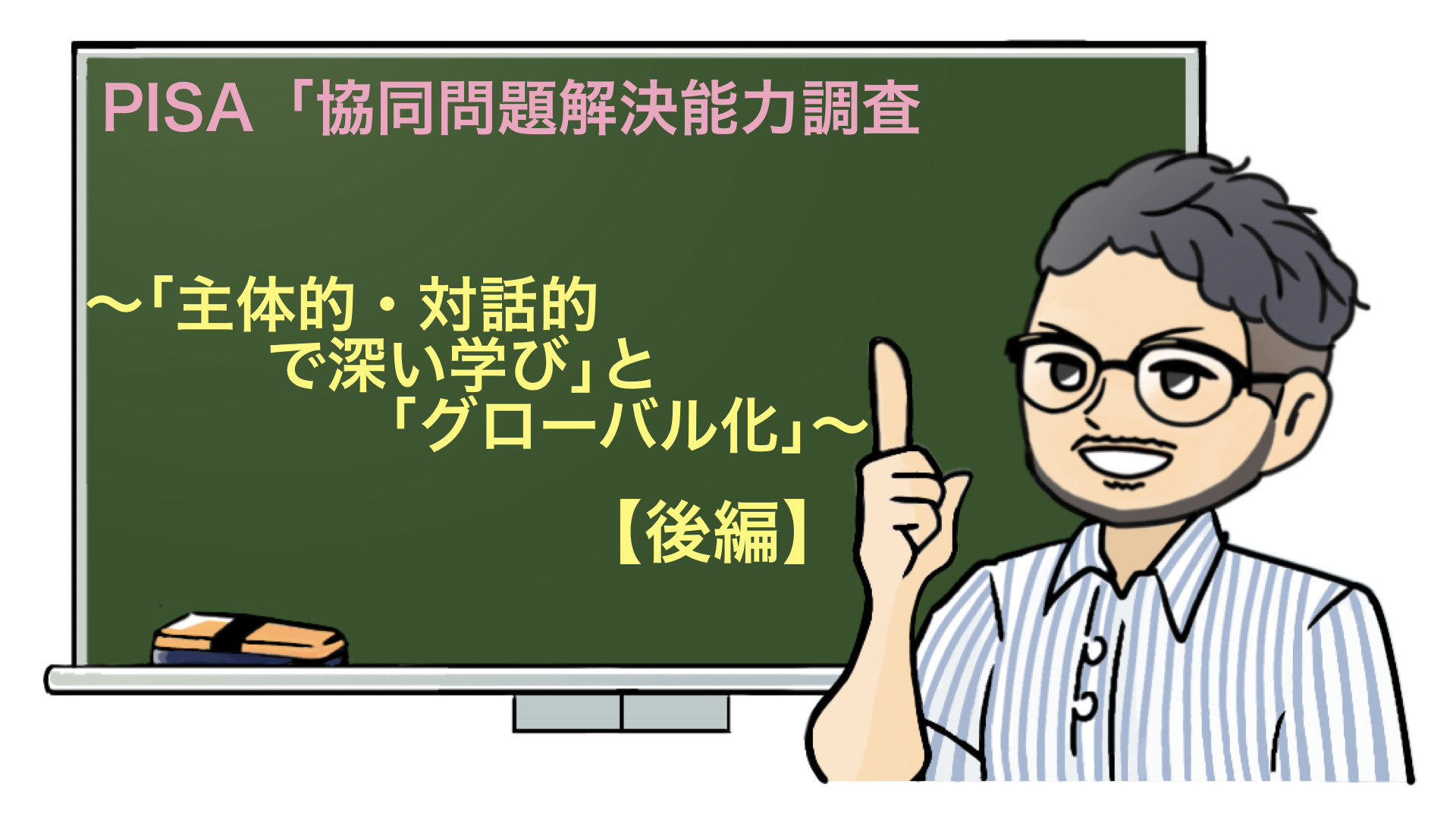



コメント