 働き方
働き方 コンプライアンス・ガバナンス・アカウンタビリティ
みなさんは、この3つの言葉は聞いたことがありますか?コンプライアンスは、最近メディアでも耳にする機会が増えました。今回は、この3つの言葉「コンプライアンス」「ガバナンス」「アカウンタビリティ」の紹介と、これらが学校にもたらす影響を一緒に考えていきたいと思います。
 働き方
働き方 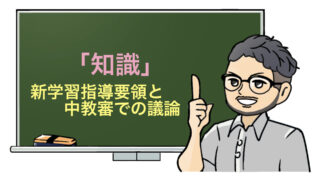 働き方
働き方 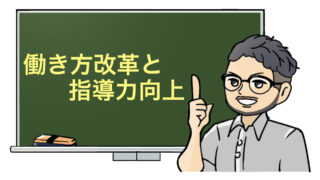 働き方
働き方 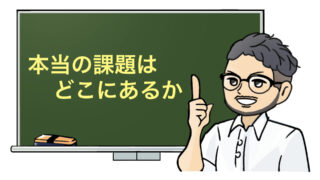 働き方
働き方 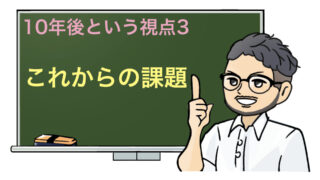 働き方
働き方 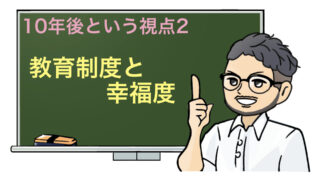 働き方
働き方 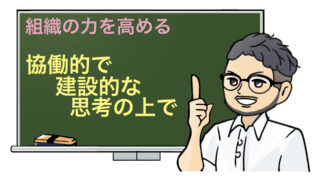 働き方
働き方  働き方
働き方  働き方
働き方 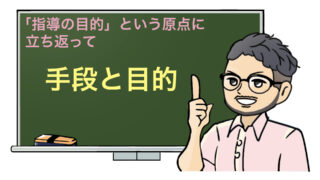 働き方
働き方